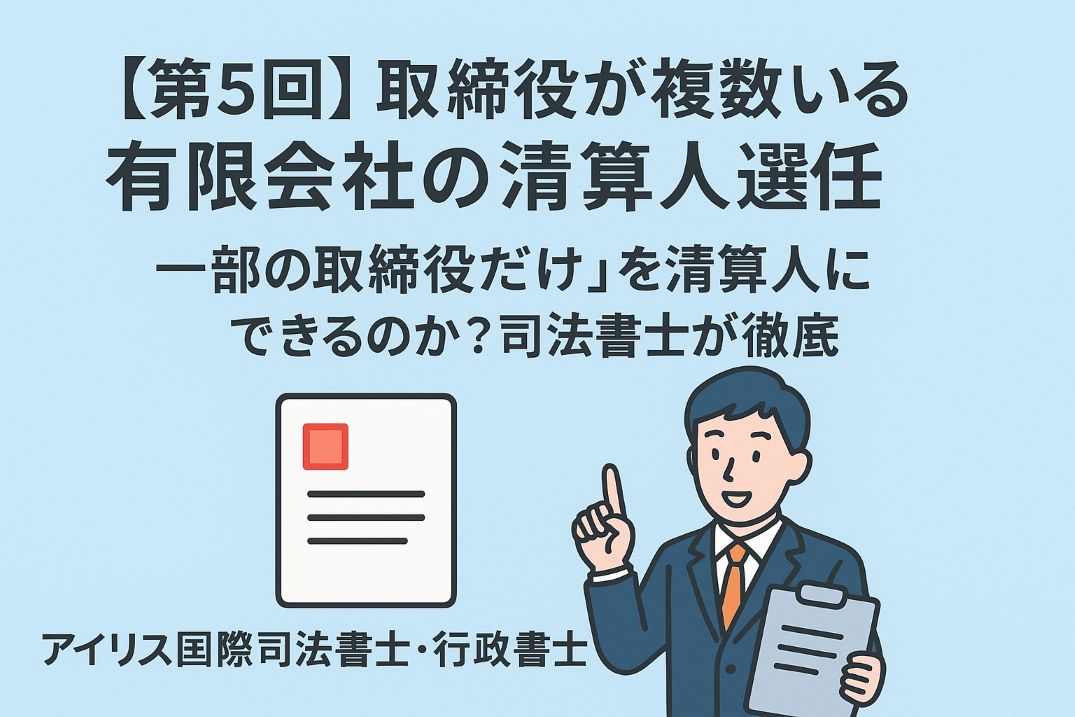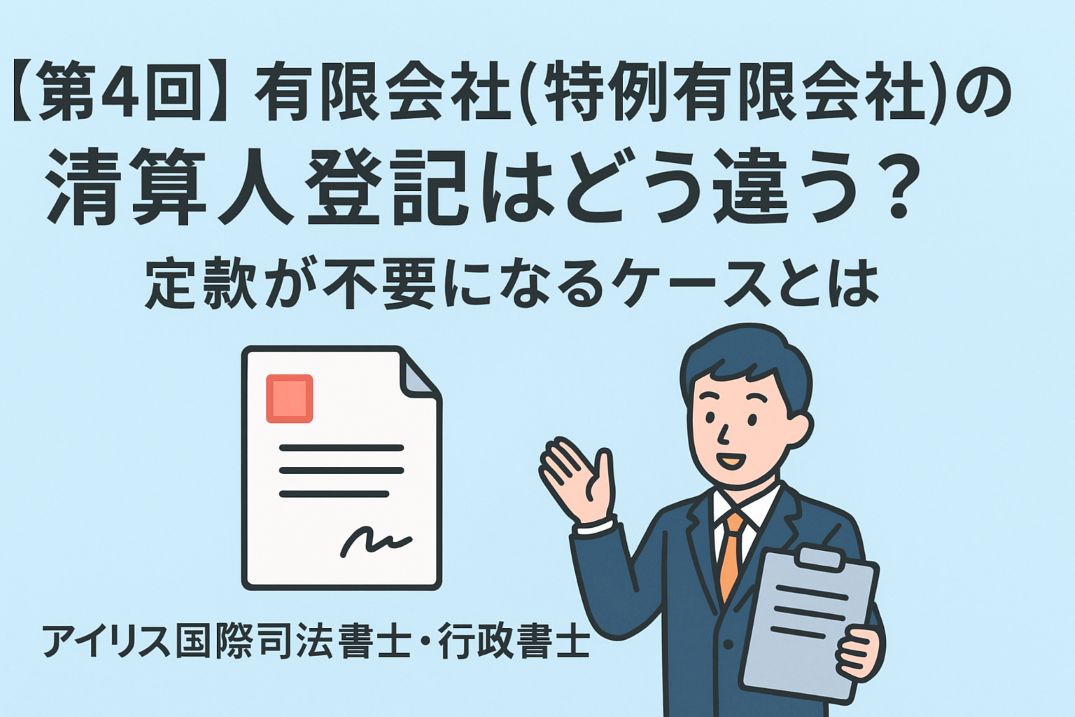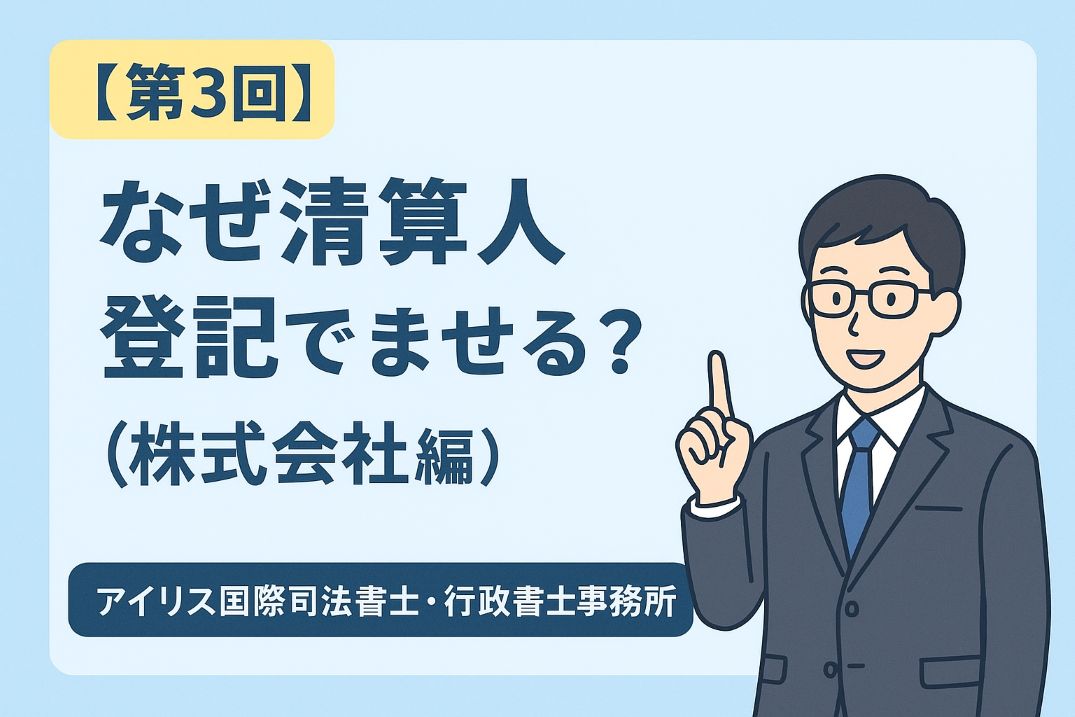取締役が複数いる有限会社(特例有限会社)で会社を解散する場合、「清算人は取締役全員なのか?」「一部の取締役だけを清算人にできるのか?」という点は、実務でもトラブルが非常に多い論点です。本記事では、会社法の規定と登記実務の両面から、清算人選任の可否と手続きのポイントを司法書士が徹底的に解説します。
【みなし解散】回避後の役員変更登記(選任懈怠と登記懈怠の違いと対応策)
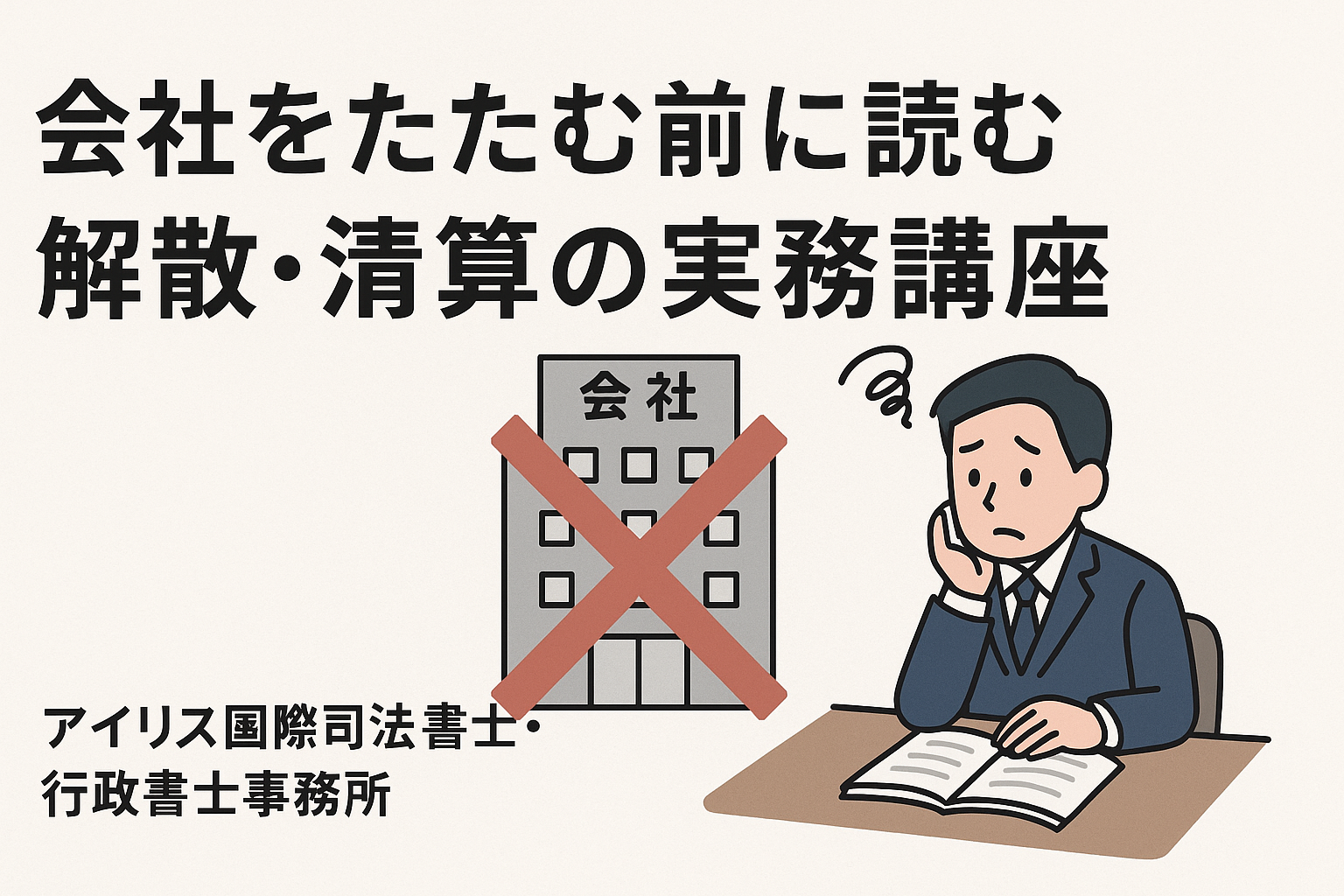
株式会社の役員変更登記は、会社法に基づき、変更が生じた日から2週間以内に行うことが義務付けられています。しかし、長期間登記が行われていない場合、法務局から「みなし解散」の通知が届くことがあります。この通知に対し、事業を継続している旨を届け出て解散を回避した後、過去に行うべきであった役員変更登記を申請する際に、「選任懈怠」と「登記懈怠」のどちらに該当するかが問題となります。本記事では、これらの違いと、それぞれの対応策について詳しく解説します。
目次
- みなし解散制度とは
- 選任懈怠と登記懈怠の定義と違い
- 選任懈怠の影響と対応策
- 登記懈怠の影響と対応策
- 過料のリスクとその回避方法
- まとめ
1. みなし解散制度とは
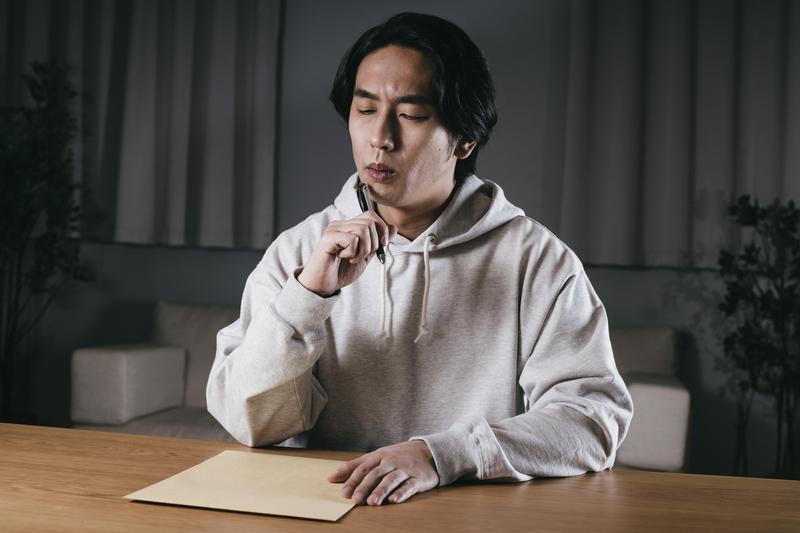
「みなし解散」とは、株式会社が最後の登記から12年間、登記簿に変更がないまま経過した場合、法務局がその会社を休眠会社とみなし、一定の手続きを経た後、解散したものと扱う制度です。この制度は、実態のない会社を整理するために設けられています。みなし解散の通知を受けた場合、事業を継続している旨を届け出ることで解散を回避することが可能です。
2. 選任懈怠と登記懈怠の定義と違い
選任懈怠とは
選任懈怠とは、役員の任期満了後に新たな役員の選任を行わず、株主総会等の手続きを怠っている状態を指します。この場合、役員の選任自体が行われていないため、登記もされていません。
登記懈怠とは
登記懈怠とは、役員の選任は適切に行われているものの、その変更登記を法定期間内に行っていない状態を指します。つまり、実質的には役員の変更があったにもかかわらず、登記手続きが遅れている場合です。
3. 選任懈怠の影響と対応策
影響
選任懈怠がある場合、任期満了後の役員は「権利義務役員」として、後任者が選任されるまでの間、引き続き役員としての権利義務を有します。しかし、登記簿上は役員が不在であるように見えるため、会社の信用に影響を及ぼす可能性があります。
対応策
選任懈怠が判明した場合、速やかに株主総会を開催し、新たな役員の選任を行う必要があります。その後、選任された役員について、就任日を明記して登記申請を行います。この際、前任者の退任日と新任者の就任日との間に空白期間が生じることになりますが、これは法的に問題ありません。
4. 登記懈怠の影響と対応策
影響
登記懈怠がある場合、法定期間内に登記を行わなかったことにより、裁判所から過料を科される可能性があります。また、登記簿上の情報が実態と異なるため、取引先や金融機関からの信用を損なう恐れがあります。
対応策
登記懈怠が判明した場合、速やかに過去の株主総会議事録等を整理し、遅れていた登記を行います。この際、過去の選任日を基準に「重任」として登記を行うことが可能です。ただし、過料の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
5. 過料のリスクとその回避方法

会社法第976条により、役員の変更登記を怠った場合、100万円以下の過料に処される可能性があります。過料の金額は、懈怠の内容や期間によって異なりますが、数万円から十数万円程度が一般的です。過料を回避するためには、役員の任期を把握し、適切な時期に株主総会を開催して選任を行い、法定期間内に登記を申請することが重要です。
6. まとめ
みなし解散の通知を受けた後、事業継続の届け出を行い、役員変更登記を申請する際には、自社の状況が「選任懈怠」か「登記懈怠」のどちらに該当するかを正確に判断することが重要です。選任懈怠の場合は、速やかに新たな役員の選任と登記を行い、登記懈怠の場合は、過去の選任に基づく登記を行うことで、会社の信用を維持し、法的リスクを回避することができます。定期的な登記簿の確認と、役員任期の管理を徹底することが、健全な会社運営には不可欠です。
役員変更登記に関する手続きや過料のリスクについて不明な点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。特に、定款の内容や会社の種類によって手続きが異なるため、正確な情報をもとに対応することが重要です。

解散・清算結了
【第4回】有限会社(特例有限会社)の清算人登記はどう違う?定款が不要になるケースとは
有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。
【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。
【第2回】清算人はどのように定める?定款・取締役・株主総会の優先順位を司法書士が解説
会社を解散すると、事業運営は停止し、財産整理を行う「清算人」が必要になります。しかし清算人は誰がどうやって決めるのか、定款・取締役・株主総会のどれが優先されるのか、誤解が多いポイントです。本記事では、清算人の定め方を司法書士の実務に基づいて徹底解説します。