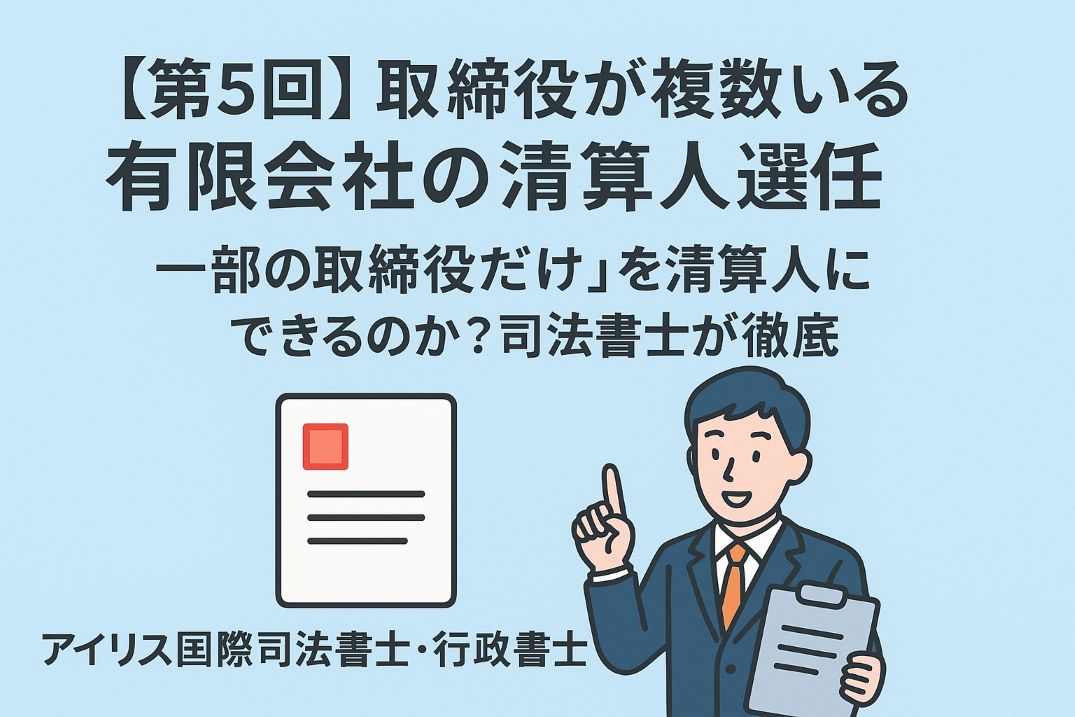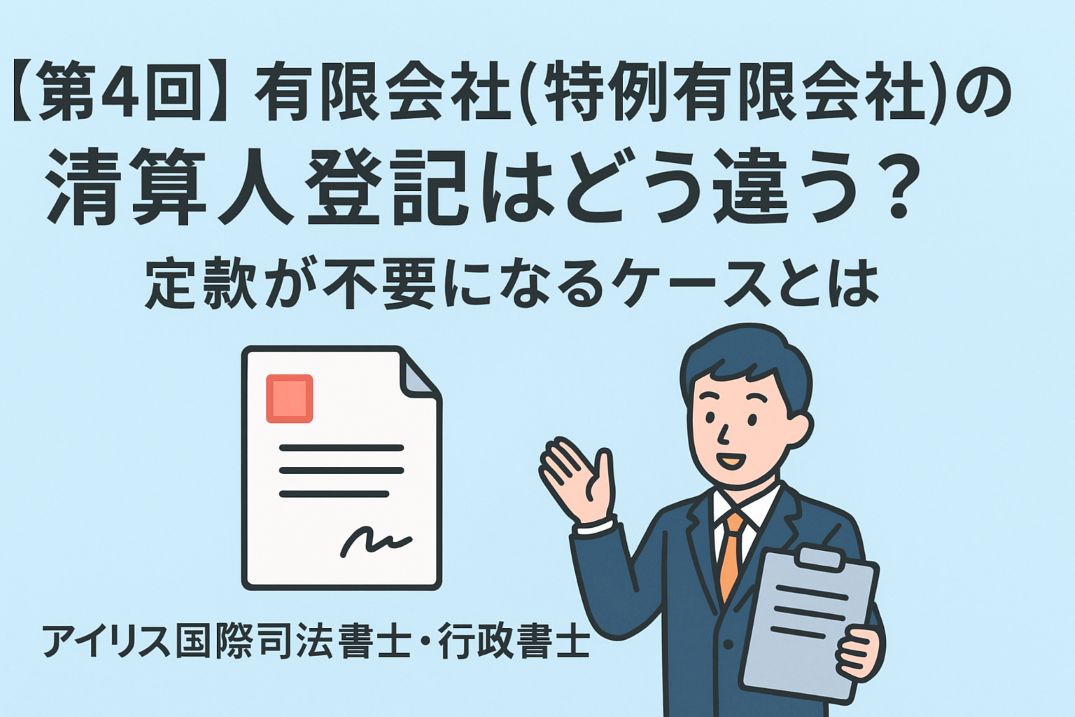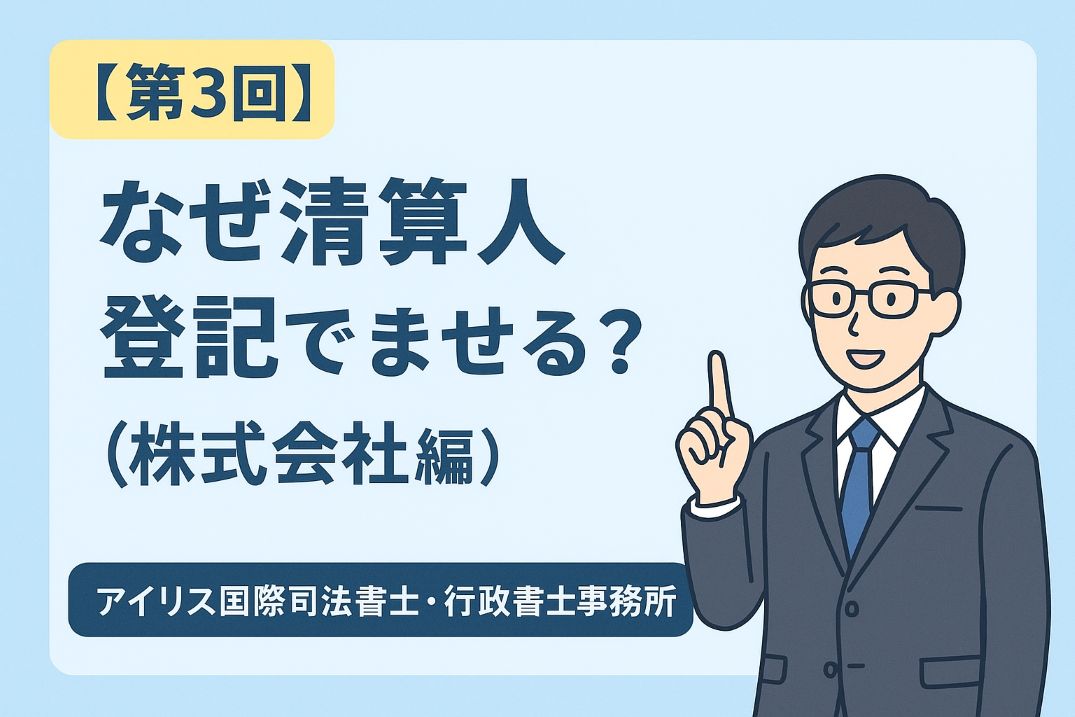取締役が複数いる有限会社(特例有限会社)で会社を解散する場合、「清算人は取締役全員なのか?」「一部の取締役だけを清算人にできるのか?」という点は、実務でもトラブルが非常に多い論点です。本記事では、会社法の規定と登記実務の両面から、清算人選任の可否と手続きのポイントを司法書士が徹底的に解説します。
【第5回】解散した会社に資産が残っていたら?清算人の責任と遺された財産の扱い方
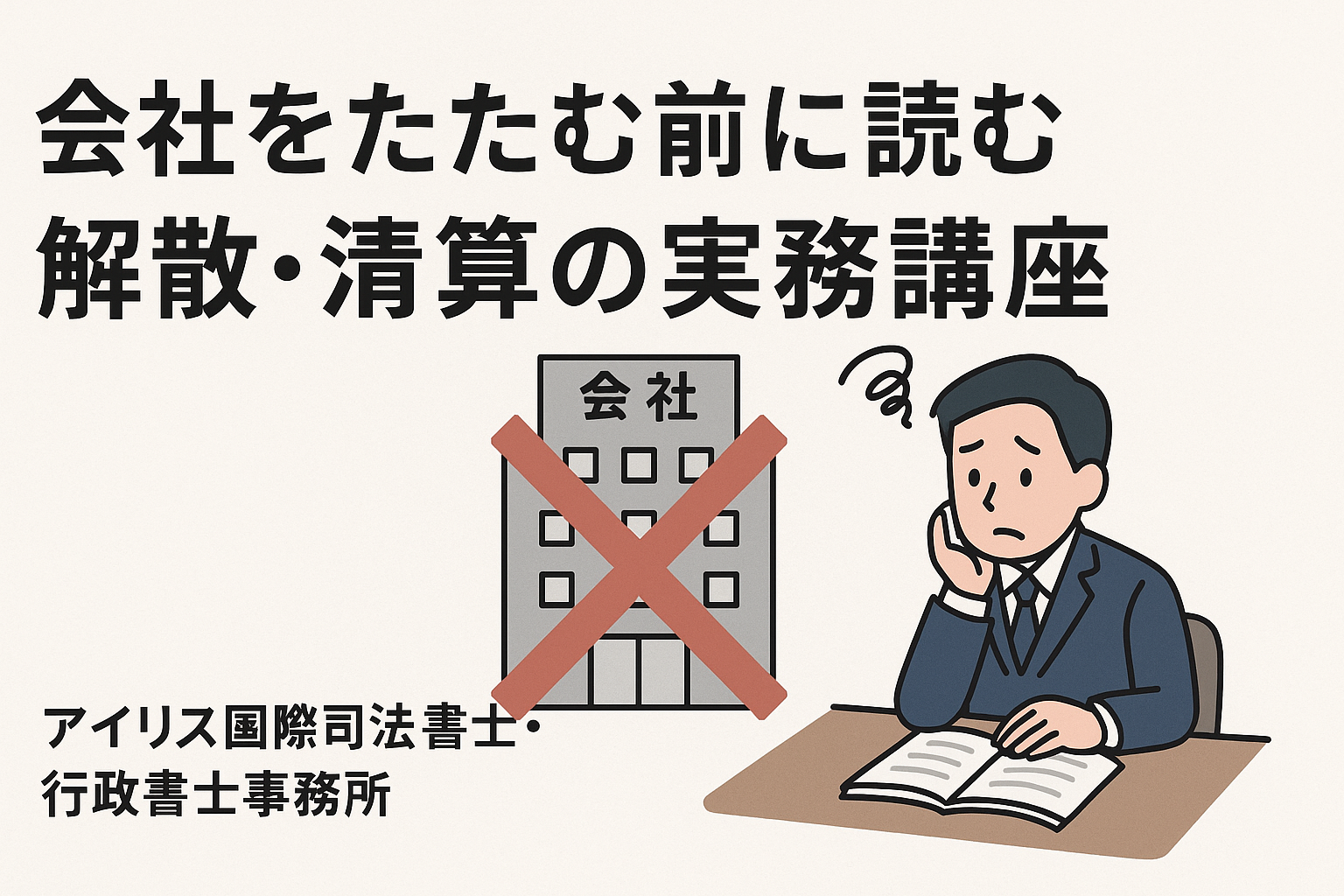
会社を解散した場合、法人格はただちに消滅するわけではなく、清算手続きが完了するまで「清算会社」として存続します。特に注意すべきなのが、会社名義の不動産や預金、売掛金などが清算手続き後に見つかった場合です。すでに清算結了の登記をしていたとしても、残余財産の存在が明らかになれば、清算人の対応が問われることになります。また、清算人の任務懈怠が原因で財産が失われた場合、個人的な損害賠償責任が問われることもあります。本記事では、会社解散後に判明した資産の扱い方や清算人の責任、再清算の可能性について、実務的な視点から詳しく解説します。
目次:
- 解散後の会社が「清算会社」として存続する理由
- 清算人の役割と責任とは
- 清算結了登記後に資産が見つかった場合の対処法
- 清算人の個人責任が問われるケースとは?
- 相続や訴訟にも影響?資産を放置するとどうなるか
- まとめ:清算は「会社をたたむ」だけでなく「責任を締めくくる」作業
1. 解散後の会社が「清算会社」として存続する理由

会社を解散すると、その時点で営業活動は終了しますが、すぐに法人格が消滅するわけではありません。会社法上、解散後は「清算会社」となり、以下の目的で一定期間存続します。
- 資産の換価(不動産・動産の売却等)
- 債権回収(売掛金の回収など)
- 債務の弁済(未払い金の支払いなど)
- 残余財産の分配(株主への分配)
これらの業務を行うのが「清算人」であり、会社の解散登記と同時に、清算人の就任登記も行われます。清算人は、法人の最終的な財産整理・義務の履行を担う、非常に重要なポジションです。
2. 清算人の役割と責任とは
清算人は、役員に代わって清算会社の代表者となり、会社の財産を整理して株主に残余財産を分配するまでの一連の業務を担います。具体的な業務には次のようなものがあります:
- 財産目録・貸借対照表の作成
- 債権者への公告と個別催告
- 資産の売却・換価
- 債務の弁済と税務申告
- 清算結了の登記申請
清算人には善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)が課せられており、不注意や職務怠慢によって損害が生じた場合には、株主や債権者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
3. 清算結了登記後に資産が見つかった場合の対処法

清算結了登記が完了し、法人格が消滅した後に会社名義の不動産や預金が見つかることがあります。たとえば、地方に放置されていた土地の存在が後から発覚したり、古い銀行口座に残高があったことが判明するケースです。
このような場合は、以下のいずれかの手続きが必要になります:
① 清算結了の登記を職権で抹消し、「清算再開」手続き
法務局に申請し、元の清算人を再任して再清算を行います。
② 家庭裁判所に「法人格再生の申し立て」
すでに清算人が死亡していたり、元清算人の所在が不明な場合に行われる方法です。
いずれの方法においても、残った財産は債務の弁済を行い、余剰があれば株主に分配されます。財産の性質や所在、法的権利関係によっては、相続人や他人に移転されることもあります。
4. 清算人の個人責任が問われるケースとは?
清算人が次のような不適切な対応を行った場合には、個人として損害賠償責任を問われる可能性があります:
- 資産を調査せず、存在を見落とした
- 債務を精査せず、未払い金を残したまま結了した
- 資産を特定の株主や第三者に不当に分配した
- 法務局や税務署に必要な報告・申告を怠った
とくに、意図的に財産を隠したり、債権者を害する行為をした場合は、民事上の責任に加えて刑事責任(特別背任など)を問われることもあります。
5. 相続や訴訟にも影響?資産を放置するとどうなるか
清算結了後に財産が放置されたままだと、さまざまな法的問題が生じるおそれがあります。
- 清算人が死亡した場合、相続人が知らぬ間に責任を問われることも
- 会社名義の不動産が相続登記できず、売却・管理が困難になる
- 税務上の申告漏れが発覚し、追徴課税や延滞税の対象に
- 債権者からの訴訟で、清算のやり直しが求められることも
したがって、清算手続きは「登記を終えれば完了」ではなく、実質的に財産がゼロであることを確認するまでが仕事なのです。
6. まとめ:清算は「会社をたたむ」だけでなく「責任を締めくくる」作業
会社を解散して清算結了登記をしたからといって、すべてが終わるわけではありません。会社名義の財産が残っていれば、それをきちんと処理しない限り、清算人や関係者の責任が問われるリスクが残ります。
清算とは単なる「終わり」ではなく、「きちんと責任をもって法人を締めくくる」ための重要なプロセスです。解散時には、必ず専門家とともに財産の洗い出しを行い、後々に問題が残らないよう慎重に進めましょう。

解散・清算結了
【第4回】有限会社(特例有限会社)の清算人登記はどう違う?定款が不要になるケースとは
有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。
【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。
【第2回】清算人はどのように定める?定款・取締役・株主総会の優先順位を司法書士が解説
会社を解散すると、事業運営は停止し、財産整理を行う「清算人」が必要になります。しかし清算人は誰がどうやって決めるのか、定款・取締役・株主総会のどれが優先されるのか、誤解が多いポイントです。本記事では、清算人の定め方を司法書士の実務に基づいて徹底解説します。