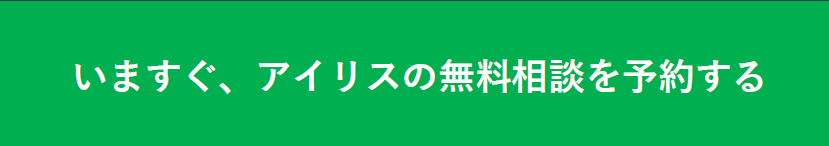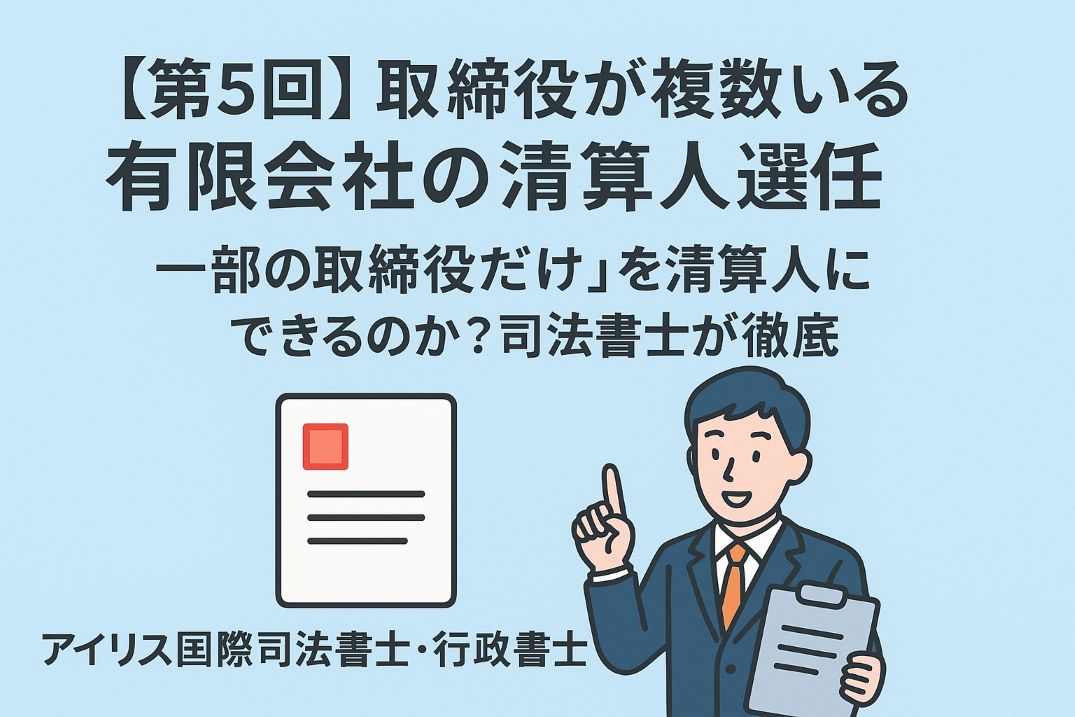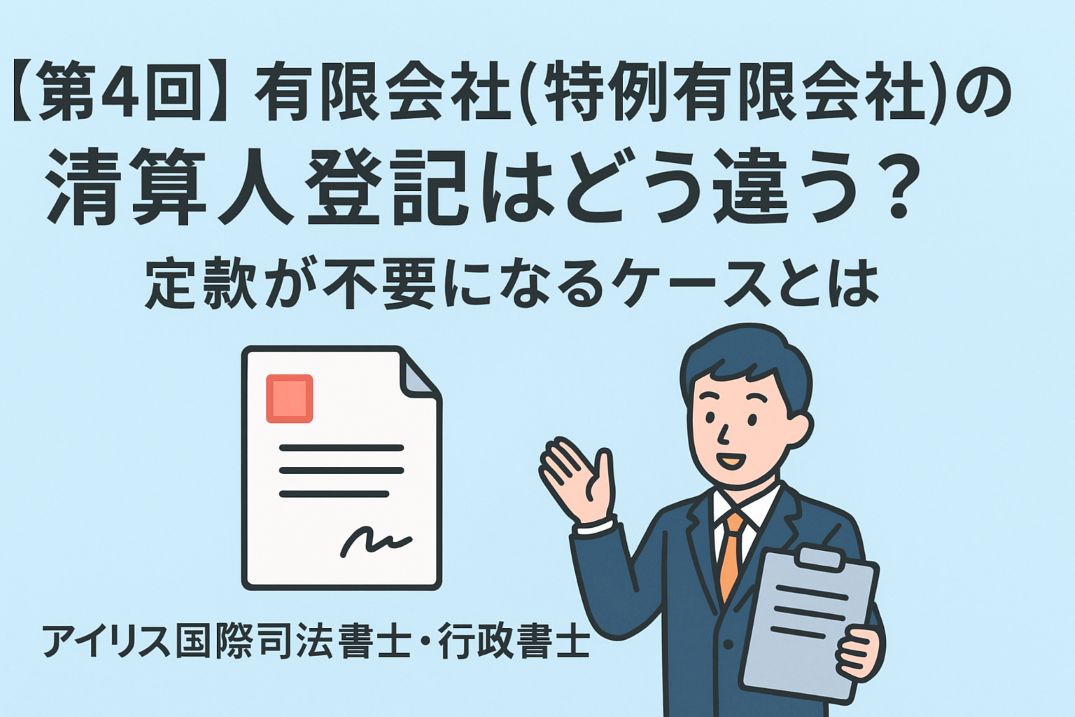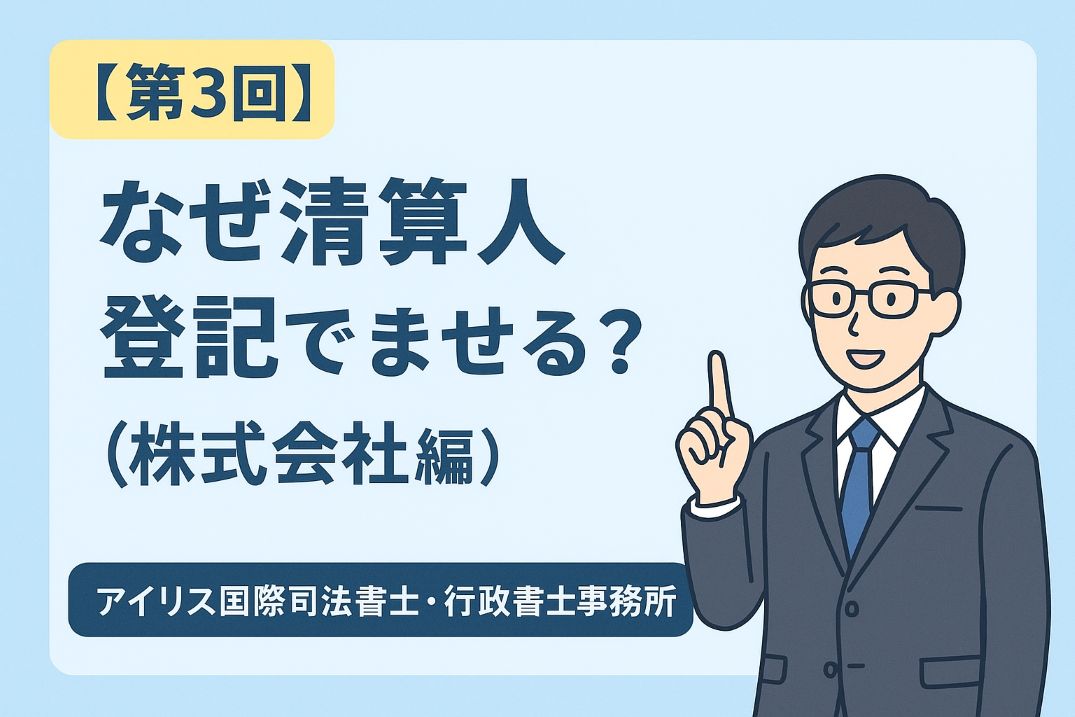取締役が複数いる有限会社(特例有限会社)で会社を解散する場合、「清算人は取締役全員なのか?」「一部の取締役だけを清算人にできるのか?」という点は、実務でもトラブルが非常に多い論点です。本記事では、会社法の規定と登記実務の両面から、清算人選任の可否と手続きのポイントを司法書士が徹底的に解説します。
【香川県で「みなし解散」の通知書が届いたら?3】職権で解散登記された後の“復活”と是正の流れ(実務ガイド)

法務局から「みなし解散により職権で解散登記をしました」と通知が届いた場合でも、一定の期間内であれば会社を「復活」させることが可能です。
ただし、再設立や新設とは異なり、復活には登記・書類・株主総会決議など複数のステップを経る必要があります。本記事では、実際に職権による解散登記が行われた後に会社を存続させるための実務的な流れを、司法書士がわかりやすく解説します。
【目次】
- 職権による「みなし解散登記」が入るとどうなるか
- 「会社継続の登記」で復活できる期限と条件
- 継続決議から登記申請までの流れ
- 登記懈怠による過料と対応の考え方
- 司法書士が伝えたい実務上の注意点
- よくある質問(FAQ)
1. 職権による「みなし解散登記」が入るとどうなるか

みなし解散制度は、12年間以上登記を行っていない株式会社を対象に、法務局が職権で「解散登記」を行う制度です(会社法472条2項)。
つまり、実際には廃業していなくても、登記が長年放置されていると「解散した」とみなされてしまいます。
この「職権による解散登記」が入ると、会社の登記簿上は「解散会社」として扱われ、以下のような制限が発生します:
- 銀行取引や契約更新が困難になる
- 新たな登記申請が原則できなくなる
- 法人名義での不動産取引や助成金申請も制限される
実質的に"会社としての活動ができない状態"となるため、早期に継続手続をとることが重要です。
2. 「会社継続の登記」で復活できる期限と条件

会社法第472条第3項により、職権で解散登記が行われた場合でも、
「みなし解散の日から3年以内」であれば、会社を復活(継続)させることが可能です。
復活(継続)登記を行うための主な条件は以下のとおりです。
- 株主総会で「会社を継続する旨の決議」を行う
- 取締役(役員)の再任または新任を決定する
- 未登記の役員変更がある場合は同時に登記する
- 解散登記の日から3年以内であること
つまり、"3年以内"という期限を過ぎると、復活ではなく新会社設立として扱われます。
この点を誤解して放置してしまうケースが非常に多いため注意が必要です。
3. 継続決議から登記申請までの流れ

実務では次のような流れで復活登記を行います。
ステップ①:株主総会の開催
まず、会社を存続させるための意思決定として、**株主総会で「会社継続の決議」**を行います。
議事録には次のような文言を記載します。
「当会社は、会社法第471条第1号により解散したものとされたが、会社法第472条第3項の規定に基づき、会社を継続することを決議する。」
この議事録は後の登記に必須となります。
ステップ②:役員の再選任または新任
長期間登記をしていなかった会社では、取締役や代表取締役の任期がすでに満了しているケースが多いです。
その場合は、再任や新任の手続きを行い、役員変更登記も同時に進めます。
ステップ③:登記書類の準備と申請
以下の書類を法務局へ提出します:
- 株主総会議事録(継続決議)
- 取締役の就任承諾書・印鑑証明書
- 登記申請書(会社継続登記)
- 登録免許税(6万円)
また、職権解散登記の写しを添付する場合もあります。
司法書士に依頼することで、書類不備や登記拒否のリスクを減らすことができます。
4. 登記懈怠による過料と対応の考え方
職権解散登記がなされる前後を問わず、役員の変更登記を怠っていた期間がある場合、
会社法976条に基づき「過料(行政罰)」が科される可能性があります。
ただし、過料は刑罰ではなく行政的な注意・是正の意味合いが強く、
反省文(陳述書)を提出することで、減額や免除となることもあります。
過料の金額は通常、数万円〜十数万円程度。(法律上は、100万円以下の過料となっています)
司法書士に相談して、経過や事情を丁寧に整理しておくことが大切です。
5. 司法書士が伝えたい実務上の注意点

- 復活は3年以内が絶対条件
→ 3年を過ぎると、新規設立扱いとなり、過去の法人格・資産が失われます。 - 登記懈怠期間の説明準備を
→ 「なぜ登記を怠ったのか」を明確にしておくと、過料処理がスムーズになります。 - 法人銀行口座の扱いに注意
→ 解散登記が入った時点で口座が凍結される場合があるため、早めの手続が必要です。 - 書類は司法書士に確認を
→ 一文字の誤りでも登記却下になる場合があります。
6. よくある質問(FAQ)

Q1. 解散登記から3年以上経っています。復活できますか?
→ できません。新たに会社を設立する必要があります。
Q2. 継続登記を行うと、過去の登記懈怠分も一緒に処理できますか?
→ はい。再任登記なども同時に申請する形で整合性を取ります。
Q3. みなし解散登記の通知書を紛失した場合は?
→ 管轄法務局で職権登記の有無を照会すれば確認可能です。

(無料相談会のご案内)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653
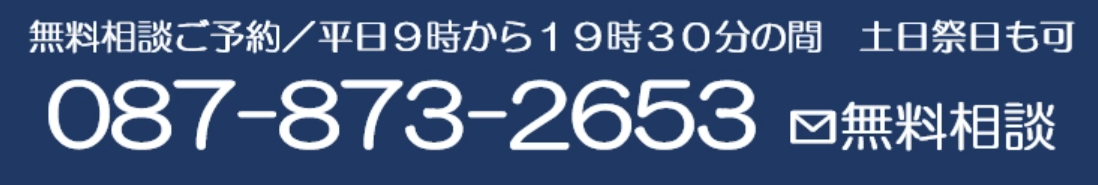
🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、会社登記・解散・継続などのご相談も承ります。
香川県内全域対応の司法書士が、実務の現場からサポートいたします。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所

解散・清算結了
【第4回】有限会社(特例有限会社)の清算人登記はどう違う?定款が不要になるケースとは
有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。
【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。
【第2回】清算人はどのように定める?定款・取締役・株主総会の優先順位を司法書士が解説
会社を解散すると、事業運営は停止し、財産整理を行う「清算人」が必要になります。しかし清算人は誰がどうやって決めるのか、定款・取締役・株主総会のどれが優先されるのか、誤解が多いポイントです。本記事では、清算人の定め方を司法書士の実務に基づいて徹底解説します。