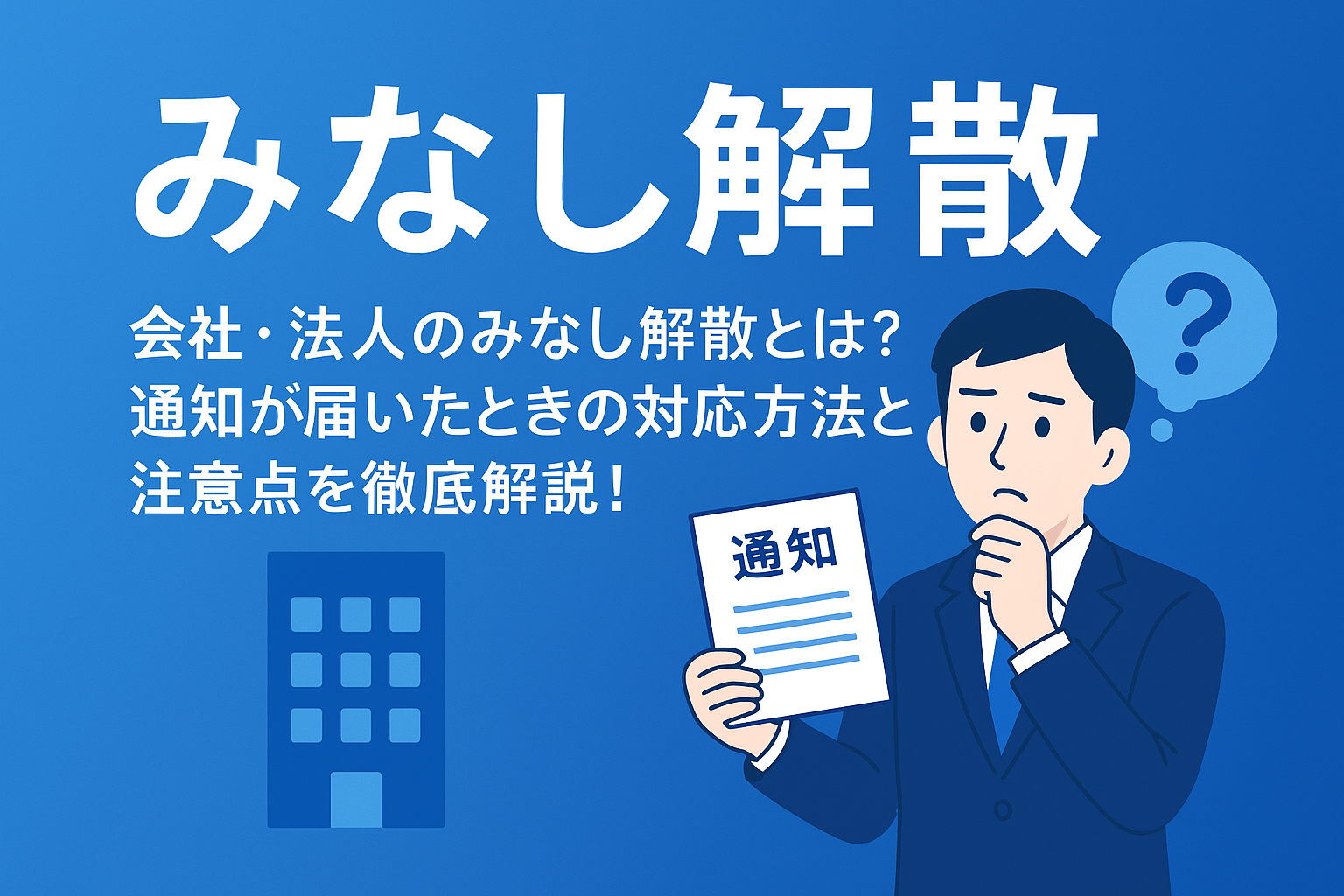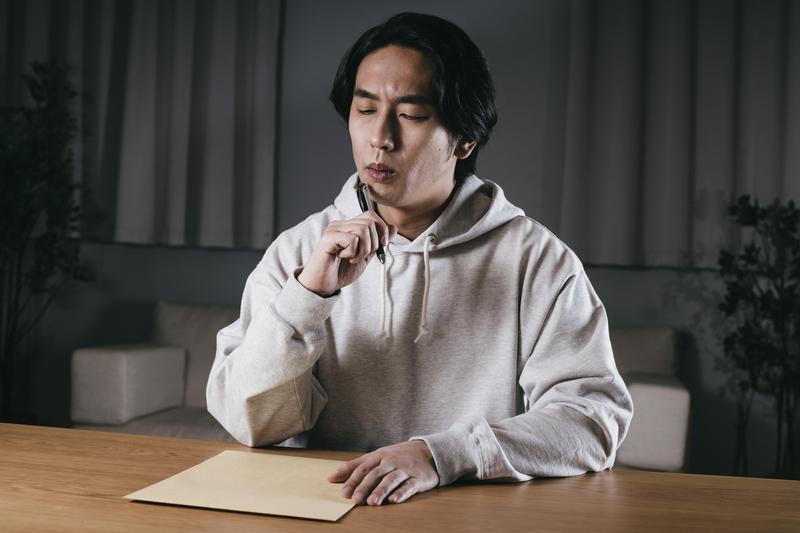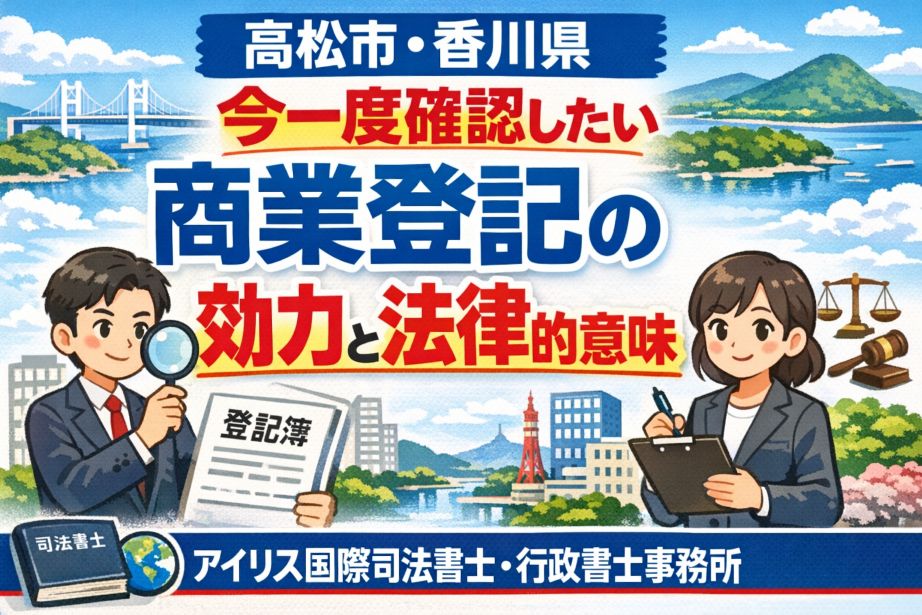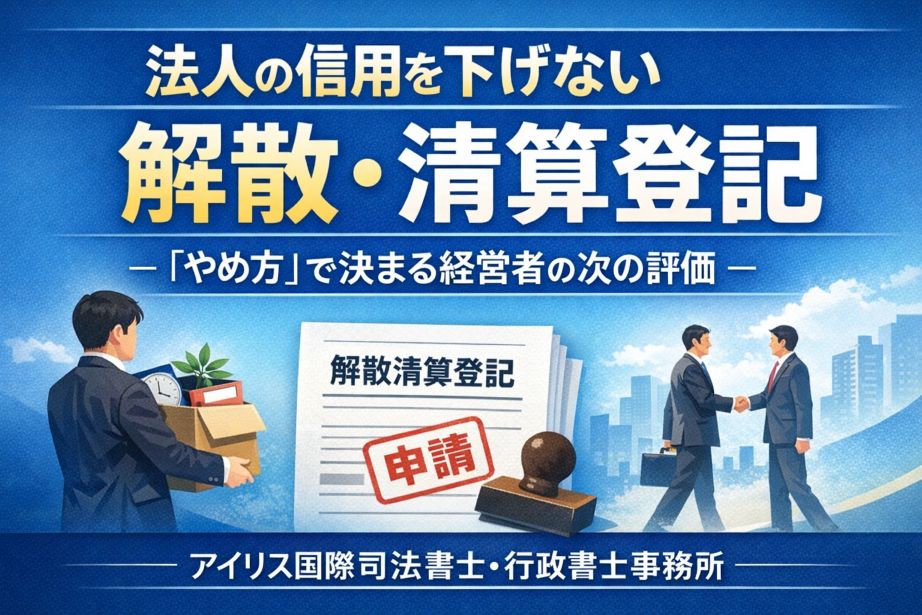みなし解散の通知を受けても、期限内に「事業を継続する意思」がある旨を法務局に届出れば、解散登記は回避できます。
具体的には、「事業継続届出書」に代表印を押し、法務局に提出します。これにより、みなし解散の対象から除外されます。
6. 継続登記の流れと必要書類
解散登記がすでにされてしまった場合でも、以下の手続きを経て、会社を「継続」させることが可能です。
- 清算人の登記(通常は元代表者)
- 株主総会での継続決議
- 役員の再任登記
必要書類としては、議事録・就任承諾書・印鑑届書・登記申請書などがあり、書式や手順を誤ると再申請になるため、専門家への相談が推奨されます。
7. 解散したことにしてしまうという選択
一方、会社を再開する予定がない場合は、解散登記をそのまま受け入れ、清算結了登記をして完全に法人を閉じるという選択肢もあります。解散登記だけでは法人格が残るため、税務署等への対応も必要です。
中途半端に放置せず、きちんと「清算手続き」を経て法人を終わらせることが、後々のトラブル回避につながります。
8. 放置してしまった場合の再生方法
すでに解散登記がされてしまっているが、事業を再開したい場合には「会社継続の登記」が必要です。これは株主総会での特別決議を経て申請するもので、再出発が可能です。
ただし、登記の空白期間が長いと、印鑑証明や履歴事項全部証明書が取れなくなることもあるため、速やかな手続きが重要です。
9. まとめとご相談のご案内
みなし解散は「通知さえ見落とさなければ回避できる制度」です。しかし、通知に気づかず放置してしまった場合でも、継続の道は残されています。どのように対応すべきか、解散を選ぶべきか、それとも事業を続けるべきか、状況に応じて適切な判断が求められます。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、みなし解散通知への対応、継続手続き、清算業務のご相談に対応しております。相談もお気軽にどうぞ。