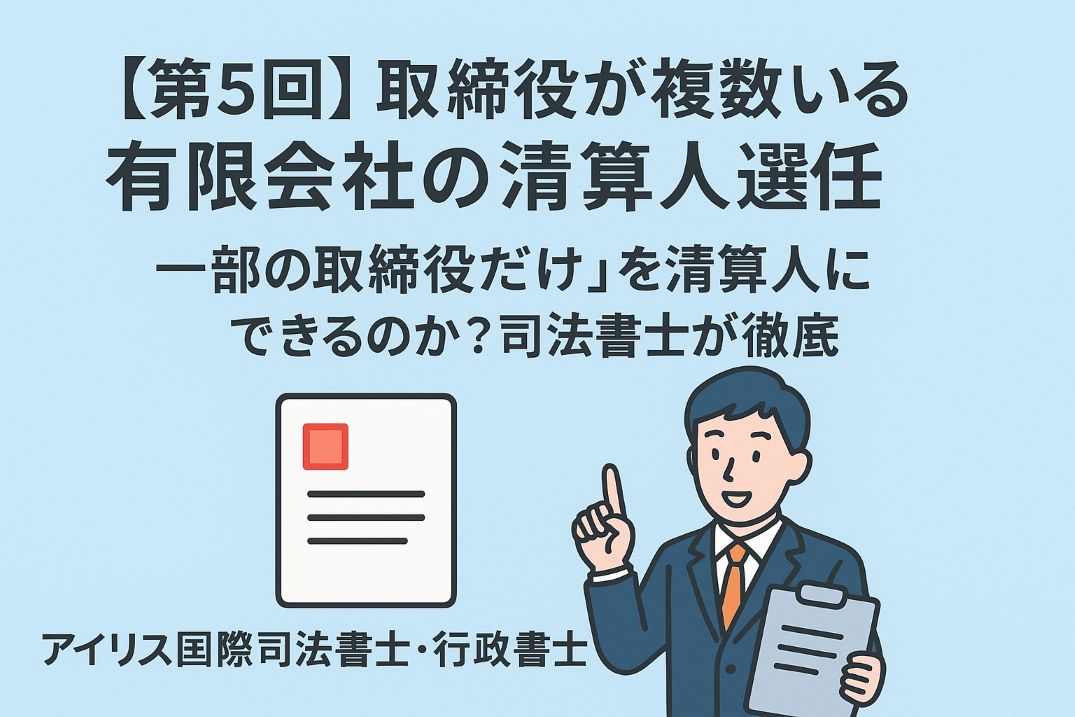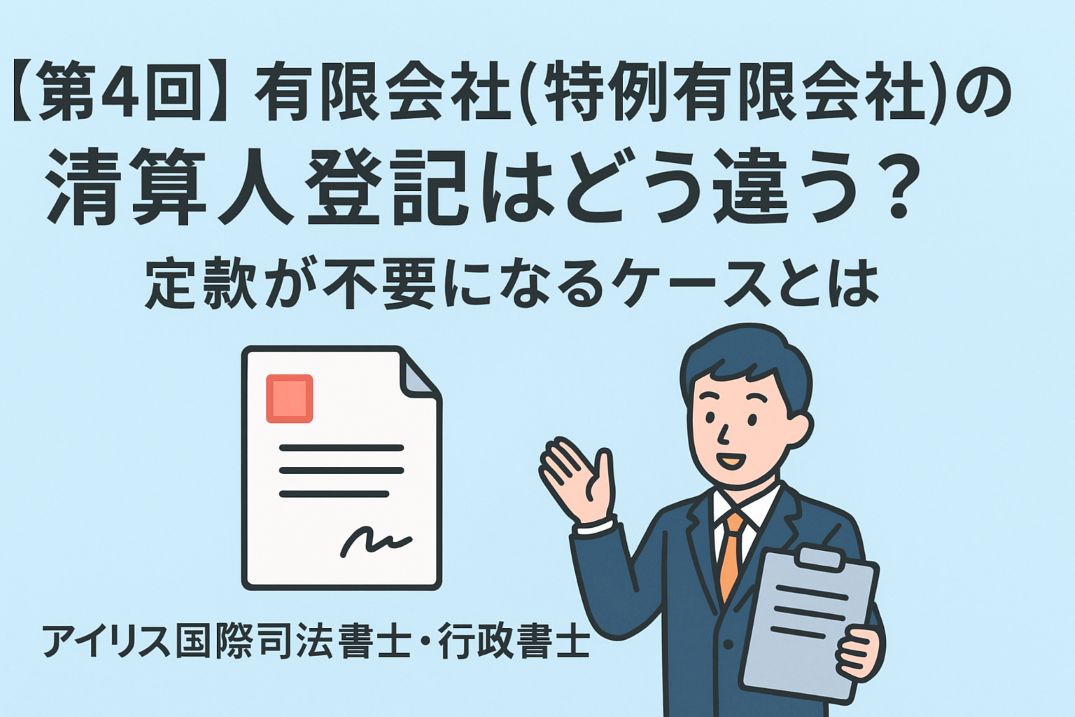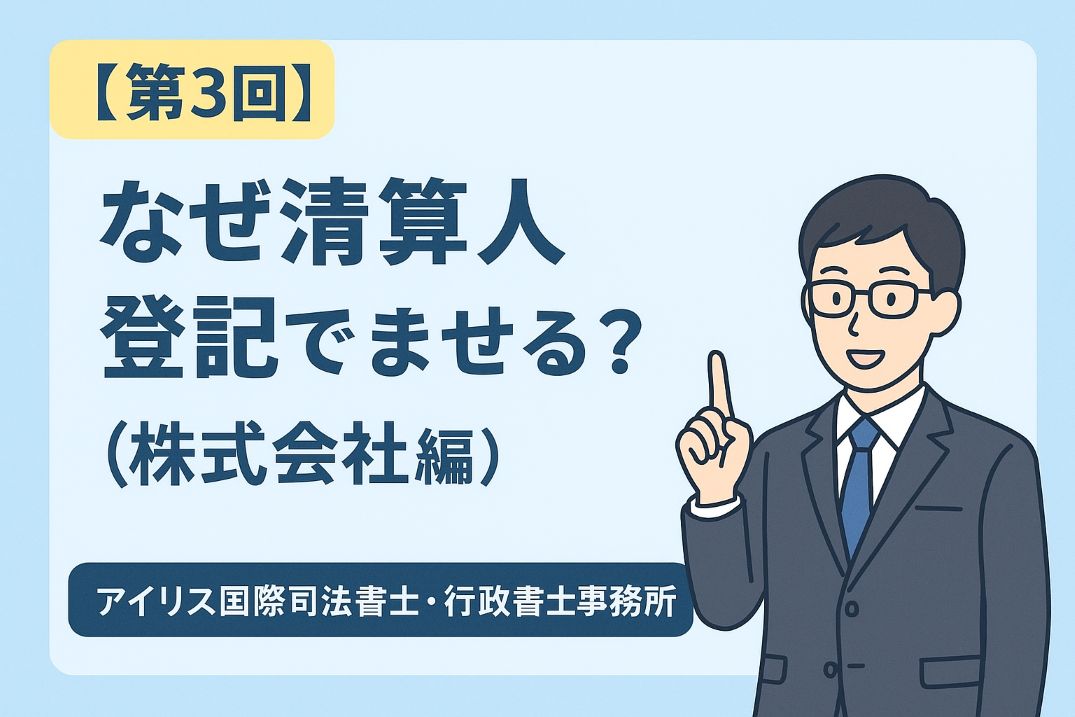取締役が複数いる有限会社(特例有限会社)で会社を解散する場合、「清算人は取締役全員なのか?」「一部の取締役だけを清算人にできるのか?」という点は、実務でもトラブルが非常に多い論点です。本記事では、会社法の規定と登記実務の両面から、清算人選任の可否と手続きのポイントを司法書士が徹底的に解説します。
【第1回】法人をやめるときに必要な「解散登記」とは?その意味と流れを解説
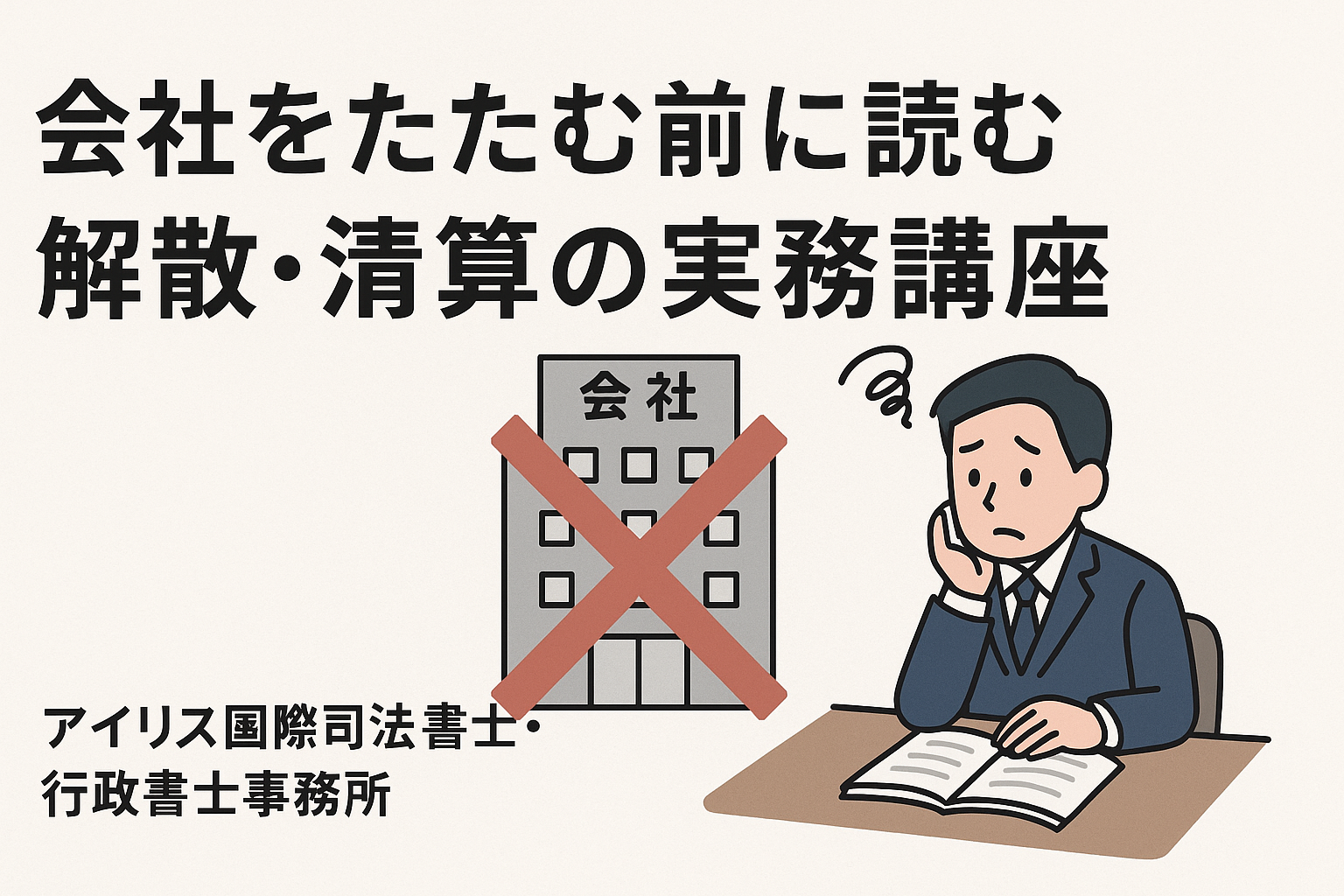
会社の経営を続けていると、「もう会社を畳みたい」「事業を終了させたい」と思うタイミングが訪れることもあります。しかし、法人の活動をやめるには、単に営業を停止するだけでは不十分です。法律上、法人格を持つ会社を終了させるには、所定の解散・清算手続きを踏まなければなりません。その最初の一歩が「解散登記」です。
この記事では、株式会社を例に、会社をやめる際に必要な「解散登記」の意味、必要書類、株主総会での決議、登記申請のタイミングなど、実務で押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
【目次】
- 解散とは?「会社を閉じる」は2段階
- 解散登記の法的意味とは?
- 株主総会での解散決議と議事録の作成
- 解散登記に必要な書類一覧
- 解散登記の期限と注意点
- 次のステップ「清算」へ
1. 解散とは?「会社を閉じる」は2段階

「会社をやめる」と聞くと、営業をやめて取引を終了するだけと思いがちですが、法人は法律によって人格を認められている存在です。よって、法律上も正式に「終了」させる必要があります。
法人をやめるには大きく分けて次の2ステップを踏みます:
- ステップ①:解散(=営業活動の終了を決定)
- ステップ②:清算(=会社の財産や債務を整理)
このうち、本記事ではステップ①の「解散」に焦点を当てて解説します。
2. 解散登記の法的意味とは?
解散とは、「今後この会社は営業を行いません」という状態に移行することを意味します。ただし、法人格そのものはすぐに消滅するわけではありません。解散してもなお、会社には「清算会社」としての法的地位が残り、未払いの債務や財産の整理、税務処理などを行う必要があります。
この「解散した」という状態を第三者に示すために必要なのが解散登記です。
解散登記が完了すると、登記簿には「解散」の旨と、清算人が代表権を持つ旨が記載されます。これによって、会社は取引先や金融機関、税務署などに対して、営業終了を法的に示すことになります。
3. 株主総会での解散決議と議事録の作成

株式会社の場合、解散を決定するには、原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法第471条1号)。
この特別決議には、以下の要件を満たす必要があります:
- 発行済株式総数の過半数の株主が出席
- 出席株主の3分の2以上の賛成
この決議で解散を決定したら、その内容を記した株主総会議事録を作成します。後に解散登記の添付書類として提出するため、議事録の形式や署名捺印などは法的要件に従って正確に作成する必要があります。
また、解散と同時に清算人を選任するのが一般的で、その人選についても議事録に記載します。清算人については次回の記事で詳しく説明します。
4. 解散登記に必要な書類一覧
解散登記の申請に際しては、法務局に以下の書類を提出します:
- 解散登記申請書
- 株主総会議事録(解散および清算人選任決議)
- 清算人の就任承諾書
- 印鑑届書(新たに清算人の印鑑を届け出る場合)
- 登録免許税(3万円)※清算人選任・就任は別途9000円必要です。
※オンライン申請にも対応していますが、添付書類の電子化や署名方法に注意が必要です。
5. 解散登記の期限と注意点
解散の決議をしたら、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行わなければなりません(会社法第915条1項)。
この期限を過ぎると、「過料」の対象となる可能性があります。
また、登記が完了しても、税務署や都道府県税事務所などへの異動届も忘れずに行う必要があります。登記と並行して、税務・社会保険など他の関係機関への手続きも計画的に進めましょう。
6. 次のステップ「清算」へ
解散登記が完了したら、次に進むのは清算手続きです。これは、会社に残っている財産や債務を整理し、最終的に法人を消滅させるプロセスです。
清算人が中心となって、債権回収・債務の支払い・残余財産の分配などを行い、すべての処理が完了した後に「清算結了登記」を行うことで法人は正式に消滅します。
この「清算」のプロセスについては、次回の記事で詳しく解説いたします。
まとめ
法人をやめるには、単に「営業をやめる」だけでなく、「解散登記」から始まる法的な手続きが必要です。株主総会での決議、議事録の作成、必要書類の準備など、登記申請には一定の準備期間が必要なため、計画的に進めることが大切です。
次回は、解散後に行う「清算人の選任と清算手続き」について、より具体的に解説していきます。

解散・清算結了
【第4回】有限会社(特例有限会社)の清算人登記はどう違う?定款が不要になるケースとは
有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。
【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。
【第2回】清算人はどのように定める?定款・取締役・株主総会の優先順位を司法書士が解説
会社を解散すると、事業運営は停止し、財産整理を行う「清算人」が必要になります。しかし清算人は誰がどうやって決めるのか、定款・取締役・株主総会のどれが優先されるのか、誤解が多いポイントです。本記事では、清算人の定め方を司法書士の実務に基づいて徹底解説します。