設立後3年で差がつく登記メンテナンス ― 放置企業と信頼される会社の決定的な違い ―
会社設立後、登記を一度も見直さないまま3年が経過している企業は少なくありません。しかし、登記情報は銀行・取引先・行政から「会社の信用」を判断される重要な資料です。本記事では、設立後3年以内に必ず確認したい登記メンテナンスのポイントと、放置した場合のリスクを実務目線で解説します。
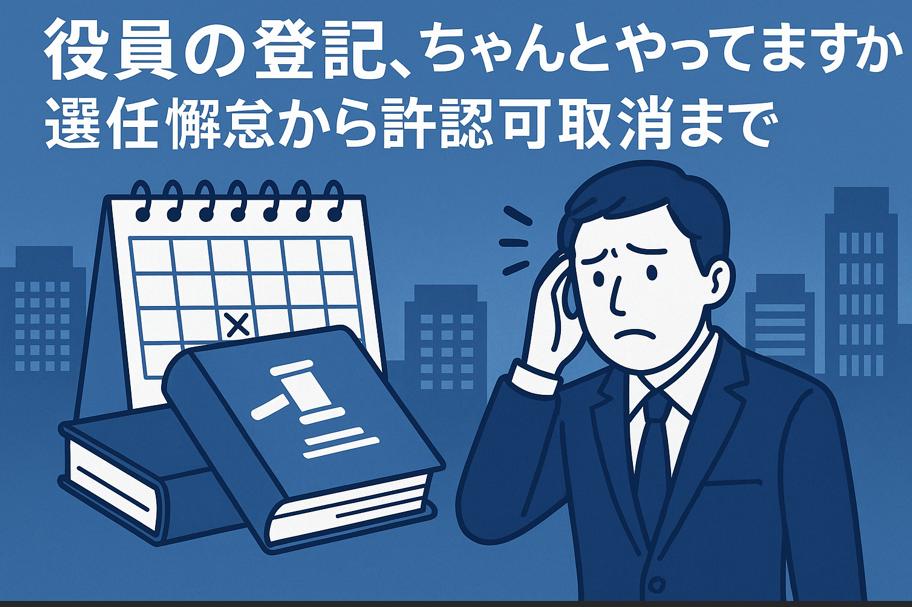
「役員の任期が切れたのに、何もしていない」――そんな状態に心当たりがある会社は要注意です。それは「選任懈怠(せんにんけたい)」という状態にあたり、単なる手続きミスでは済まされない法的・実務的な問題を抱えている可能性があります。選任懈怠は、会社が役員の任期満了などに伴い、新たな選任をせず放置している状態であり、最悪の場合、行政からの許認可取消や事業継続不能という深刻な事態を招くおそれもあります。本記事では、登記懈怠との違い、選任懈怠のリスク、そして回避するための実務対応までを詳しく解説します。
【目次】
1. 選任懈怠とは何か?

選任懈怠とは、取締役や監査役などの役員について、任期満了や辞任・死亡等によりその職が空いたにもかかわらず、新たな選任をせずに放置している状態をいいます。会社法では、取締役や監査役などは原則として任期満了ごとに株主総会などで選任し直す必要があり、その決議をしなければならないとされています。
この選任手続きをしないまま会社の機関構成を欠いた状態で放置すると、取締役会や株主総会の決議そのものが無効になるおそれもあり、重大な機能不全に陥ります。
2. 登記懈怠との決定的な違い
前回の記事で解説した「登記懈怠」と混同されがちですが、両者はまったく異なる問題です。
登記懈怠は書類提出の問題ですが、選任懈怠は会社運営の根本に関わる「ガバナンス上の重大な欠陥」と言えます。
3. 選任懈怠がもたらす法的・実務的なリスク

選任懈怠は以下のようなリスクを会社にもたらします。
このように、選任懈怠は「経営が止まる」「事業が継続できない」といった重大な結果をもたらしかねません。
4. 許認可事業者が特に注意すべき理由

選任懈怠が最も深刻な影響を及ぼすのは、行政の許認可を受けて事業を行っている企業です。
たとえば、建設業、宅地建物取引業、金融関連業などの業種では、「誰が役員であるか」「役員に欠格事由がないか」といった点を許認可の条件として厳しく審査しています。
このため、任期満了のタイミングで役員の選任決議を怠ってしまうと、その期間に役員の不在(空白期間)が生じることになり、
「正当な代表者が存在しない期間があった」として、行政庁からの許認可が取消されるおそれもあるのです。
しかも、過去にさかのぼって後日株主総会で決議をしても、「空白があった事実」は消せません。形式を後から整えても、行政庁の判断で取り返しのつかない事態となる可能性があります。
5. 選任懈怠を防ぐためにやるべきこと
選任懈怠を防ぐには、会社の役員任期を正確に把握し、**「次の株主総会で選任しなければならない役員は誰か」**を事前に確認しておく必要があります。
以下のような実務対応をおすすめします。
特に「再任だから変更はない」と思いがちな再任登記も、法律上は義務である点を見落としがちです。再任の場合も選任決議と登記申請が必要です。
6. まとめ:見落としが許されない「会社の生命線」
登記懈怠が「手続きミス」であるとすれば、選任懈怠は「機関不全」という会社の根幹を揺るがす問題です。任期切れを放置したままでは、会社の意思決定の正統性が疑われ、許認可を失い、会社としての存続にすら影響を及ぼしかねません。
特に許認可事業者は、行政庁に対して「役員構成が適切であること」を常に証明し続ける責任があります。
任期と選任は、会社経営の「生命線」です。
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、ふと気がつけば任期が切れていた……というケースも少なくありません。今一度、自社の役員構成と任期を見直し、懈怠がないか確認することを強くおすすめします。
次回は、「許認可取消」など、実際に生じた選任懈怠によるトラブル事例をもとに、さらに実務的な観点で解説します。

会社設立後、登記を一度も見直さないまま3年が経過している企業は少なくありません。しかし、登記情報は銀行・取引先・行政から「会社の信用」を判断される重要な資料です。本記事では、設立後3年以内に必ず確認したい登記メンテナンスのポイントと、放置した場合のリスクを実務目線で解説します。
これまで会社や法人の設立登記は、法務局が開庁している日に登記申請を行い、その申請日が設立日として登記簿に記録されるのが原則でした。ところが令和8年2月2日から、申請者の希望に応じて土日祝日・年始休日などの「行政機関の休日」も会社等の設立日として登記簿に記載できる制度が始まります。この改正は、設立日を縁起の良い日や記念日にしたいというニーズに対応したものです。
会社設立時に何気なく決めてしまいがちなのが「代表者の肩書」と「権限」です。登記上の役職と実際の役割がズレていると、契約が無効になったり、銀行手続きで止まったりすることがあります。本記事では、商業登記と実務の視点から、代表者の肩書・権限をどう設計すべきかを分かりやすく解説します。
会社設立時に決める「本店住所」は、単なる所在地ではありません。銀行口座開設、融資、許認可、取引開始など、さまざまな場面で会社の信用を判断する材料として見られています。自宅、バーチャルオフィス、賃貸オフィスのどれを選ぶかによって、設立後の実務が大きく変わることもあります。本記事では、本店住所の選び方を商業登記と実務の両面から解説します。