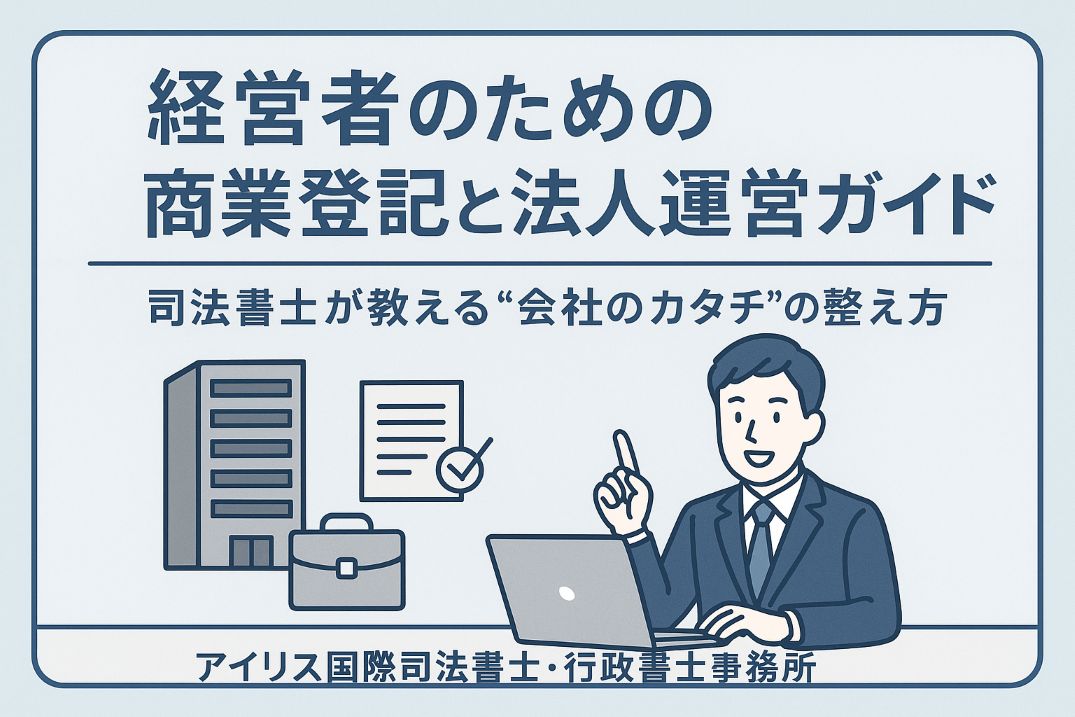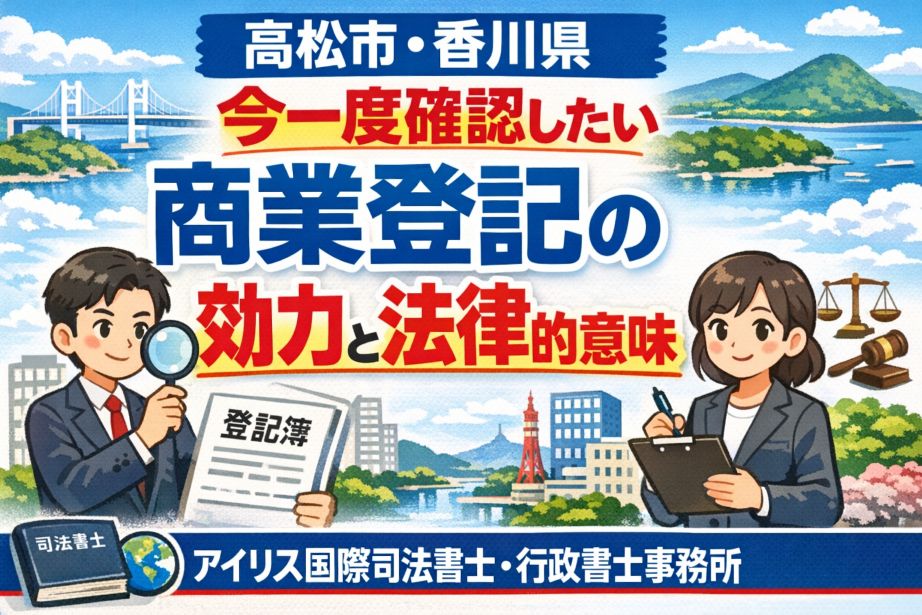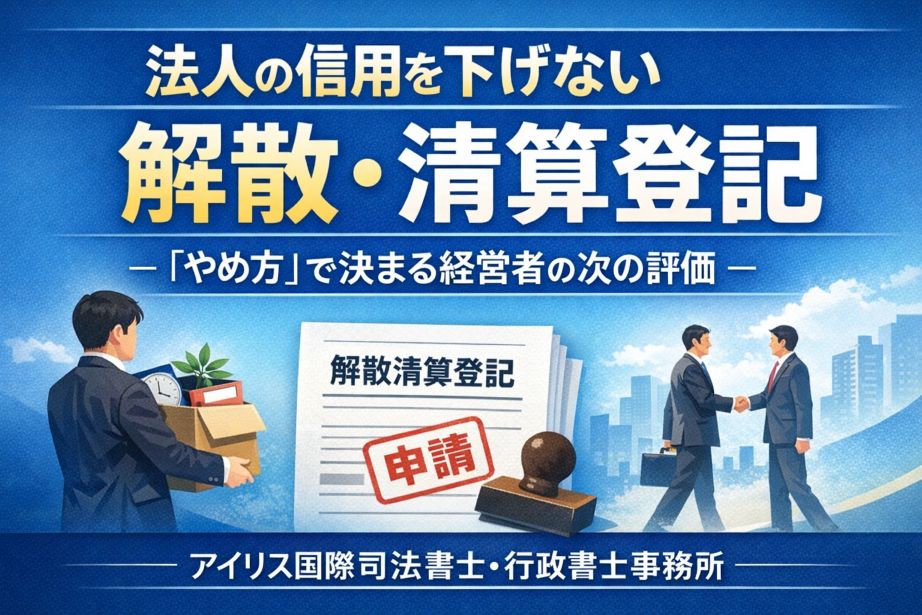副業法人では**合同会社(LLC)**を選ぶケースが増えています。
合同会社のメリット
- 設立費用が安い
- 決算公告が不要
- 小規模な事業に向いている
ただし、業界によっては「株式会社のほうが信用される」ことも事実です。
選び方の基準
- 対外的信用が必要 → 株式会社
- コストを抑えたい/小規模で十分 → 合同会社
司法書士としては、
**"取引先がどちらを求めるか"**が最も重要なポイントだと感じます。
8. 副業法人の設立実務——司法書士が見る注意点
① 会社の住所(本店所在地)
自宅を本店にする場合、
・賃貸の使用制限
・大家さんの承諾
・バーチャルオフィスの可否※業種によっては、許可・認可されないケースがあります。
などを確認する必要があります。
② 事業目的の設定
副業法人では複数の事業を並行するケースが多く、事業目的を広めに設定する必要があります。
しかし"広すぎる目的"は逆に融資や許認可で評価が下がる場合もあるため、慎重な設計が重要です。
③ 本業との利益相反の回避
会社員が副業法人を作る際は、
・就業規則
・競業避止
の観点で一定の配慮が必要です。
④ 社会保険の取り扱い
法人化すると、原則として社会保険加入が必要です。
これを理解していないと"法人化したら逆に手取りが減った"という誤算につながります。
9. まとめ:法人化は「目的」と「管理能力」で判断する
副業・小規模ビジネスでの法人化は、信用力の向上や契約面のメリットがあり、有効な選択肢です。
しかし、節税だけを目的にすると負担ばかり増えてしまいます。
法人化は次の2つで決めるのが最適です。
① 事業の目的(どのような取引がしたいか)
② 管理能力(会社運営の手間を負担できるか)
この2点が明確であれば、小規模でも法人化が大きな武器になります。