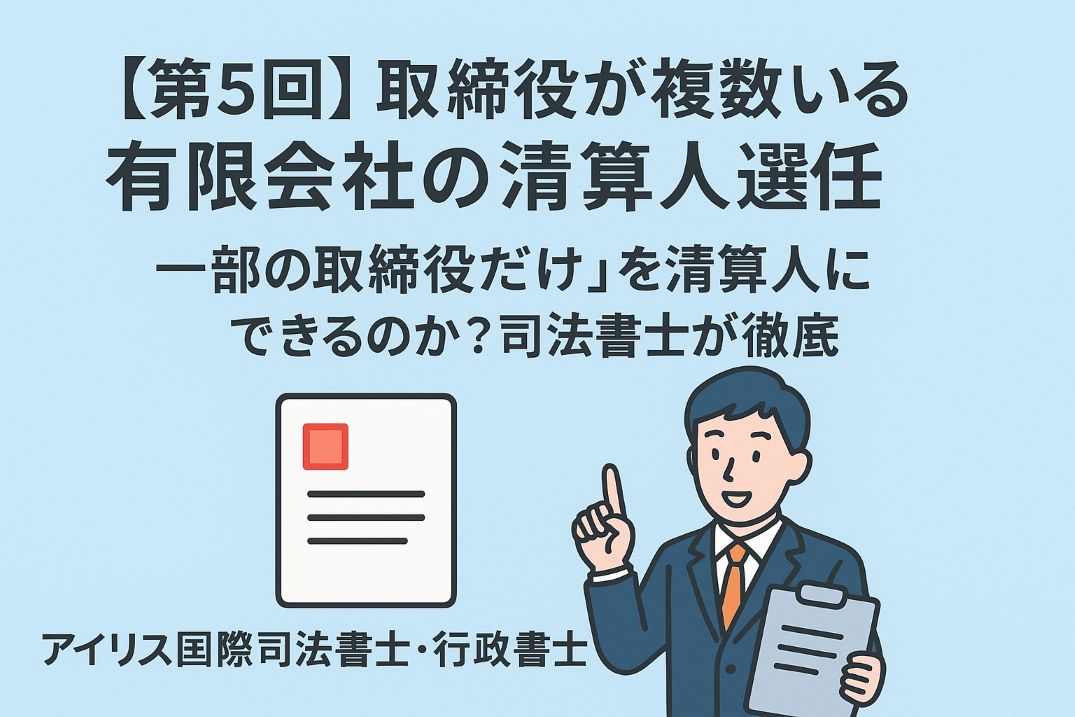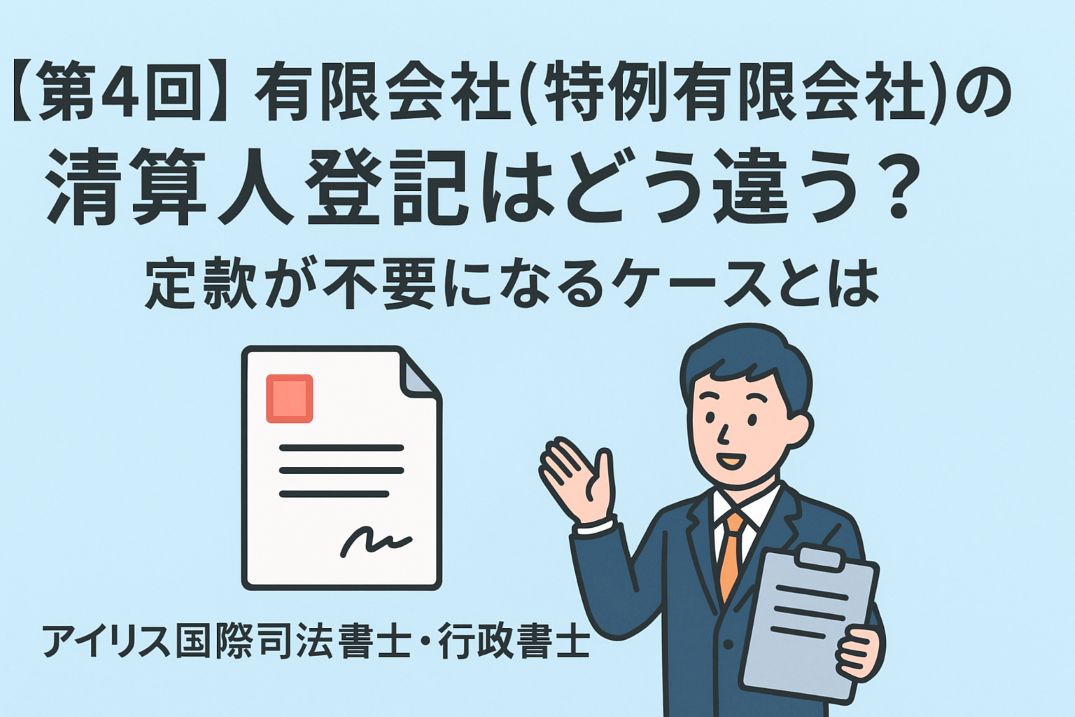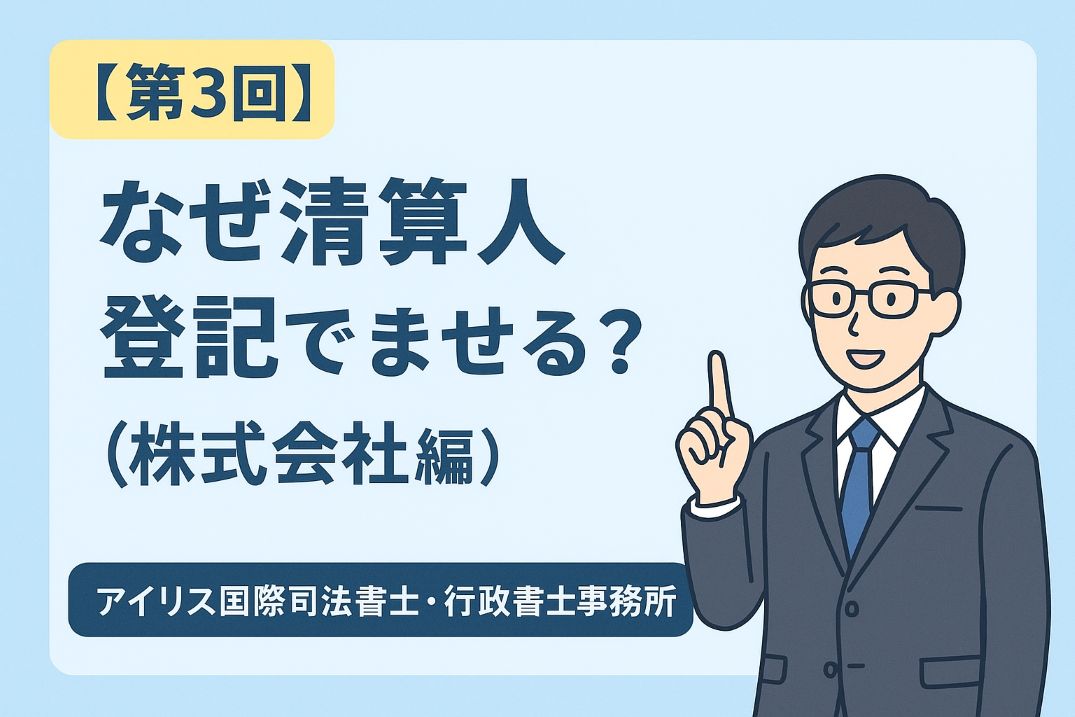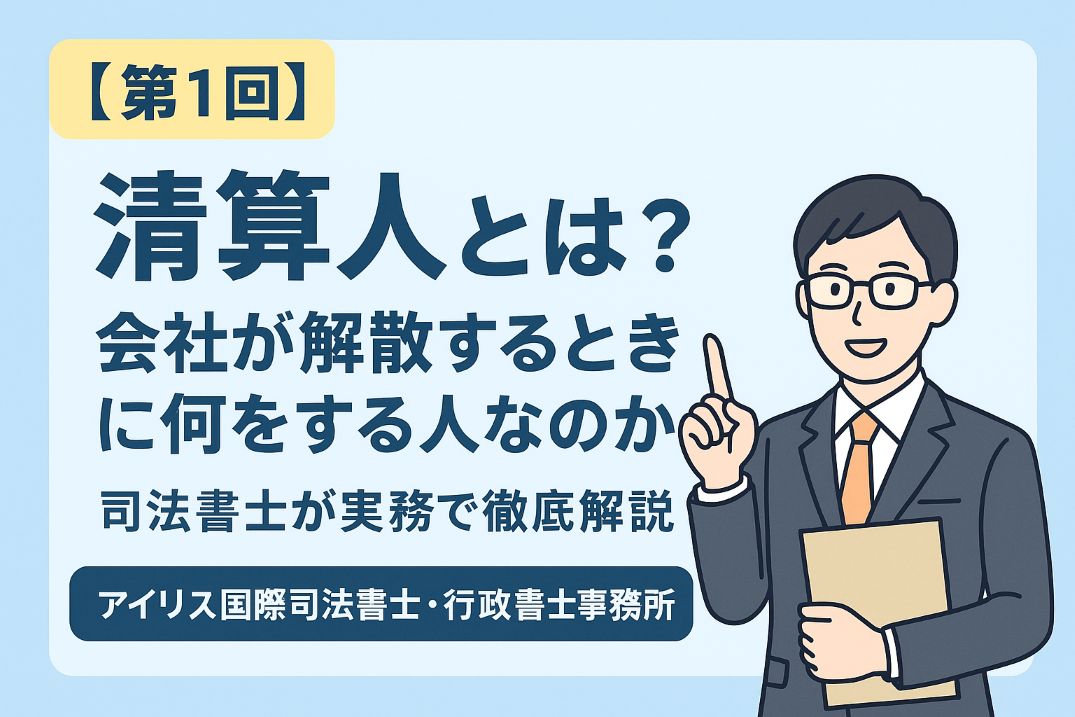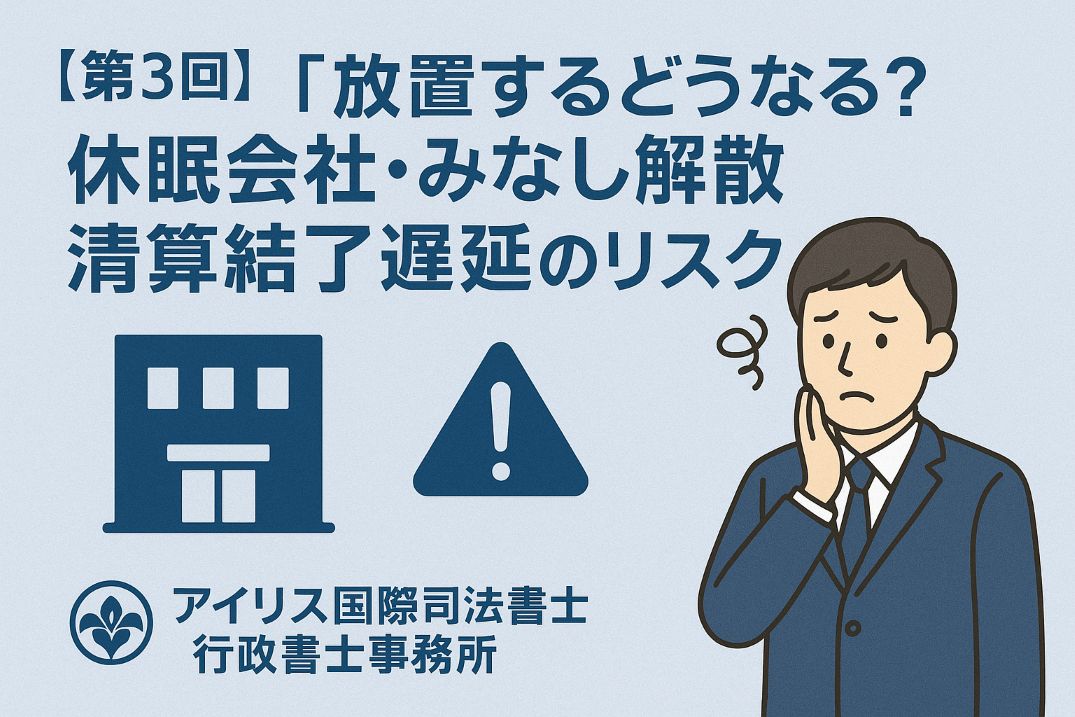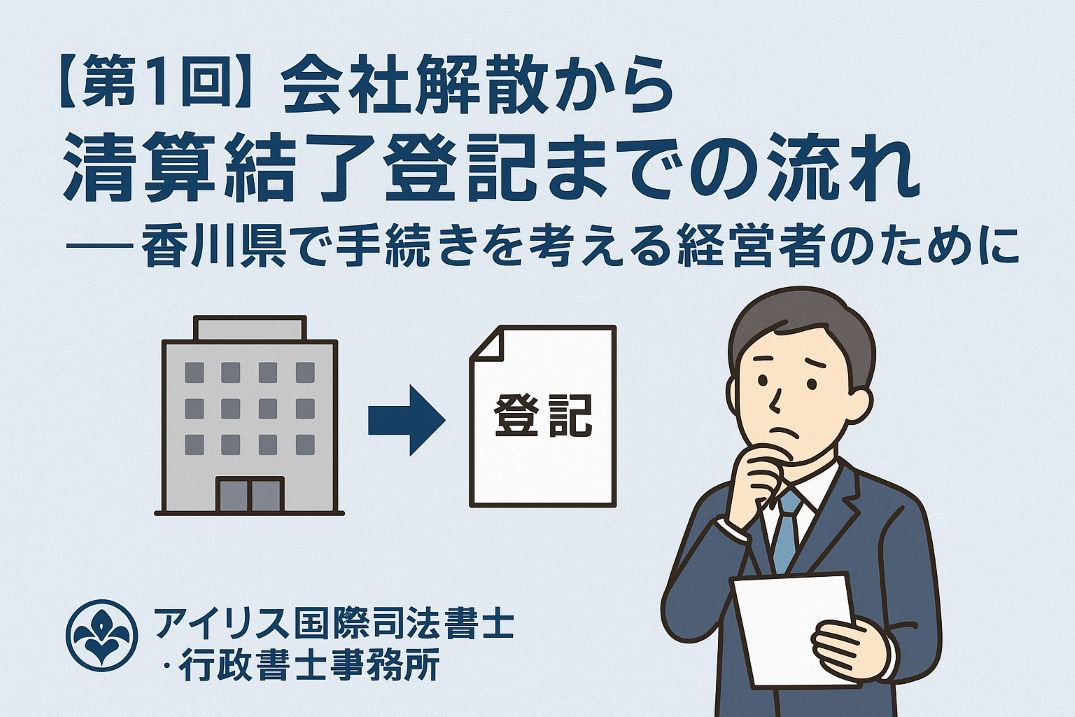取締役が複数いる有限会社(特例有限会社)で会社を解散する場合、「清算人は取締役全員なのか?」「一部の取締役だけを清算人にできるのか?」という点は、実務でもトラブルが非常に多い論点です。本記事では、会社法の規定と登記実務の両面から、清算人選任の可否と手続きのポイントを司法書士が徹底的に解説します。
解散・清算結了登記など

「アイリスDE会社じまい」〜会社を円満に締めくくるためのサポート〜
「もう会社をたたみたい」「事業は終了したが、登記や手続きがわからない」。
そのようなお悩みをお持ちの方に向けて、香川県高松市のアイリス国際司法書士・行政書士事務所では、法人の解散から清算結了までをトータルにサポートするサービス 「アイリスDE会社じまい」 をご提供しています。
こんな方におすすめです
長年動かしていない会社を整理したい
今後の事業継続を考えていないが、何から始めたらいいかわからない
株主総会や精算人の手続きなど、段取りが不安
税理士・会計士と連携したワンストップ対応を希望している
みなし解散の通知を受け取ったが対応に困っている
会社の清算後、登記の結了までしっかり終えたい
香川県高松市や近隣エリアで信頼できる専門家を探している
医療法人だが、どうやって廃業すればいいのかわからない
解散登記と清算人の選任

会社を閉じる際、まず行うべきは「解散」の登記です。
通常、株主総会で解散を決議し、同時に「清算人」を選任する必要があります。清算人は、会社の資産や負債の整理、債権者への通知・公告など、清算業務の責任を担います。
当事務所では、解散および清算人就任(または選任)の登記手続きを、迅速かつ正確に代行いたします。
定款や議事録のチェックから登記申請まで、すべてお任せいただけます。
官報公告と2か月の債権者保護期間
解散後、清算人が就任すると「官報公告」によって債権者に対する通知を行います。
この公告から2か月間、債権者が債権を申し出る期間が設けられます。この期間中に債権者からの申し出がなければ、清算手続きの終結へと進みます。
「アイリスDE会社じまい」では、官報公告の手配も含め、必要なスケジュールをしっかり管理し、ご依頼者さまに安心して進めていただける体制を整えています。
清算結了登記と税理士との連携

2か月の期間が経過した後、残余財産の分配または残余がないことの確認が必要です。
この際、税務上の処理や証明書類の作成が必要となるため、税理士との連携が不可欠です。
当事務所では、提携税理士と連携し、必要に応じてご紹介も可能です。残余財産がない旨の証明書を整えたうえで、清算結了登記の手続きまで丁寧にサポートいたします。
香川県高松市を中心に対応
「アイリスDE会社じまい」は、香川県高松市を中心に、周辺地域の法人様からも多数ご依頼をいただいております。
中小企業・合同会社・個人事業主の法人化後の解散など、さまざまなケースに対応可能です。
まずはお気軽にご相談を
「会社じまい」は単なる登記手続きではなく、経営者の人生や思いを締めくくる大切なプロセスです。
私たちはそのお気持ちに寄り添いながら、確実な手続きと安心の対応でサポートいたします。
香川県高松市で会社の解散・清算をご検討中の方は、ぜひ**「アイリスDE会社じまい」**へご相談ください。初回相談は無料です。

【第4回】有限会社(特例有限会社)の清算人登記はどう違う?定款が不要になるケースとは
有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。
【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。
【第2回】清算人はどのように定める?定款・取締役・株主総会の優先順位を司法書士が解説
会社を解散すると、事業運営は停止し、財産整理を行う「清算人」が必要になります。しかし清算人は誰がどうやって決めるのか、定款・取締役・株主総会のどれが優先されるのか、誤解が多いポイントです。本記事では、清算人の定め方を司法書士の実務に基づいて徹底解説します。
【第1回】清算人とは?会社が解散するときに何をする人なのか ― 司法書士が実務で徹底解説
会社が解散すると、通常の「取締役」は職務を終え、代わりに「清算人」が会社の後処理(清算業務)を担当します。本記事では、清算人が何をする人なのか、誰がなるのか、実務上の注意点まで司法書士がわかりやすく解説します。中小企業や閉鎖会社でも役立つ内容です。
【第3回】「放置するとどうなる?休眠会社・みなし解散・清算結了遅延のリスク」
「登記をしないまま会社を放置してしまった…」
そんな状態が長く続くと、法務局から「みなし解散」扱いを受け、会社が強制的に閉鎖される可能性があります。本記事では、香川県の登記実務の現場から、清算結了を怠った場合のリスクや再生方法を司法書士がわかりやすく解説します。
会社の清算が完了したら、最後に行うのが「清算結了登記」です。
しかし実際には、「どんな書類が必要?」「登録免許税はいくら?」「香川県ではどこに出す?」といった疑問が多く寄せられます。
この記事では、香川県で清算結了登記を行う際の必要書類・費用・注意点を、司法書士の視点でわかりやすく整理します。
【第1回】会社解散から清算結了登記までの流れ ──香川県で手続きを考える経営者のために
香川県で会社を閉じようと考えたとき、「解散登記」「清算人の選任」「清算結了登記」という3段階の手続きが必要になります。これらを正しく進めないと、法人格が残ったまま放置され、税務署や法務局からの指摘につながることも。本記事では、香川県内での会社解散から清算結了登記までの流れを、司法書士がわかりやすく解説します。
法務局から「みなし解散により職権で解散登記をしました」と通知が届いた場合でも、一定の期間内であれば会社を「復活」させることが可能です。
ただし、再設立や新設とは異なり、復活には登記・書類・株主総会決議など複数のステップを経る必要があります。本記事では、実際に職権による解散登記が行われた後に会社を存続させるための実務的な流れを、司法書士がわかりやすく解説します。
── 2か月以内に行う「事業継続の届出」と、過料を避けるための正しい手順
【香川県で「みなし解散」の通知書が届いたら?1】放置せずにまず確認すべき3つのこと
突然、法務局から「みなし解散に関する通知書」が届き、不安になっている方も多いのではないでしょうか。
「会社を閉めた覚えはないのに」「放っておくとどうなるの?」──そんな疑問に、香川県の司法書士が地域実務の視点からお答えします。この記事では、通知書を受け取った後に最初に確認すべき3つのポイントと、やってはいけない対応例を紹介します。
早めに正しい手順を踏めば、会社を守ることも可能です。
第5回:解散から清算結了までの流れと高松市での実務ポイント
会社が「解散」すると、すぐに法人格が消滅するわけではありません。清算手続を経て初めて「消滅」となります。解散から清算結了までの流れは複数の登記や公告を伴い、時間的にも法的にも一定のプロセスを踏む必要があります。本記事では、株式会社・有限会社を問わず「解散から清算結了までの手続の流れ」と、高松市で実務を行う際の注意点を司法書士が解説します。